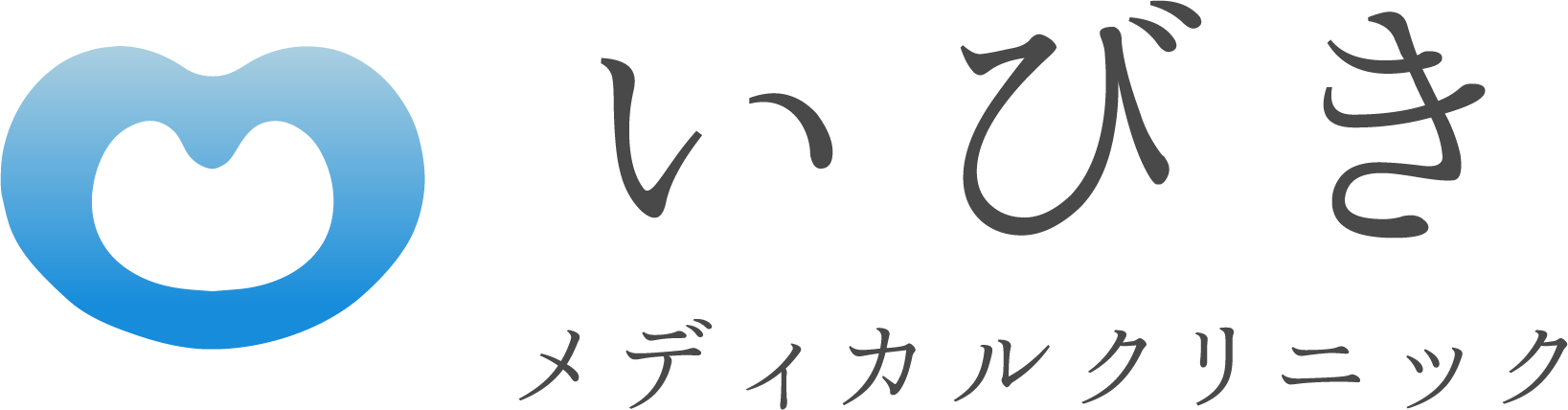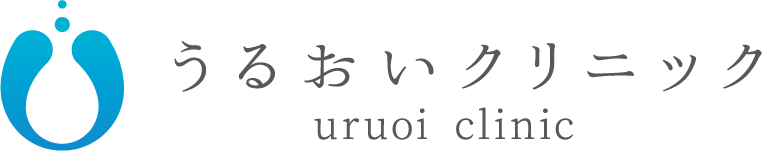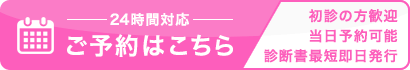双極性障害(躁うつ病)は、躁状態とうつ状態が現れる精神疾患です。うつ病や不安障害など他の疾患と間違えられることも多く、自己判断により症状を放置していると悪化する恐れがあります。
この記事では、双極性障害(躁うつ病)のセルフチェック診断や間違えられやすい疾患、病院での診断方法などを解説します。症状に不安のある方は、ぜひ参考にしてみてください。
こんな症状は双極性障害(躁うつ病)かもしれません

以下のような症状がみられる場合、双極性障害の可能性があります。まずは症状をチェックしてみましょう。
- 異常なほどハイテンションになる
- 活動的になる
- イライラしやすくなる
- 話が支離死滅になる
- 強い憂うつ状態が続く
- 元気だったのにいきなり無気力になる
- 死にたくなる
これらの症状が交互にみられる場合、双極性障害(躁うつ病)かもしれません。
双極性障害は、適切な治療をしないと再発リスクが高まってしまう精神疾患です。人間関係の悪化や社会的信用の損失など、私生活にも影響を起こし得るので、心当たりがある場合は一度専門医に相談することをおすすめします。
双極性障害(躁うつ病)とは
双極性障害(躁うつ病)とは、気分が高揚する躁状態と気分が落ち込むうつ状態を繰り返す精神疾患です。躁状態の程度により「双極I型障害」「双極II型障害」に分類され、I型は異常なほどのハイテンション、Ⅱ型は調子が良い程度のハイテンション、という違いがあります。
また、うつ状態は自他ともに症状を自覚しやすいですが、躁状態は自覚しにくく治療が遅れるケースがあることを知っておきましょう。
下記記事では双極性障害(躁うつ病)についてさらに詳しく解説しています。
双極性障害(躁うつ病)と診断される3つの症状

双極性障害(躁うつ病)は、「躁状態」「うつ状態」「混合状態」の3つ症状がみられる場合に診断されます。
以下では、それぞれの状態における具体的な症状を解説します。
躁状態の症状
躁状態では、異常なほどの興奮や過活動がみられます。
また、ハイテンションになるだけではなく、突然の喧嘩やハイリスクな投資などの問題行動を起こすことも少なくありません。
躁状態の具体的な症状は、以下の通りです。
- 衝動的に買い物やギャンブルをするようになる
- 話す速度が以上に早くなる
- 通常ではしないような大胆な行動に出る
- 睡眠時間が短くなる
- 疲労を感じにくくなる
- 根拠のない自信を語るようになる
- 性に対して奔放になる
うつ状態の症状
うつ状態では、激しい気分の落ち込みや意欲低下などの、うつ病と同様の症状がみられることが特徴です。
うつ状態の具体的な症状は、以下の通りです。
- 普段は楽しめていたことに対して興味がなくなる
- 何をするにもエネルギーが湧かず、常に疲れている
- 自殺願望が芽生えるようになる
- 食欲が湧かなくなる
- 会話のスピードが遅くなったり、受け答えが疎かになったりする
- 原因不明の倦怠感や胃の不調が続く
- 過眠や不眠に悩まされる
混合状態の症状
混合状態とは、躁状態とうつ状態の症状が同時に現れる症状のことです。
躁状態と鬱状態が切り替わるときにもみられ、気分は興奮しているのに強い不安感を感じるため、自殺リスクが高まります。
混合状態の具体的な症状は、以下の通りです。
- 頭では活動的なのに体が動かない
- テンションは高いのに涙が出てくる
- 落ち込んだ気分の中でさまざまな思考が浮かぶ
- 気分の落ち込みと焦りが同時にやってくる
双極性障害 (躁うつ病)をセルフチェック診断テスト

以下の質問①の症状に1つ以上当てはまり、なおかつ質問②の症状に4個以上当てはまる場合、双極性障害(躁うつ病)の可能性があります。
質問①
- 明らかに異常な高揚や過活動が1週間以上継続している
- 以前より怒りっぽくなった
質問②
- どこからともなく力が湧いてきて、何でもできる気がする
- 睡眠時間が2時間程度でも問題ない
- 口数が増えた
- 常に何らかの思考が頭の中をかけめぐっている
- 気が散ってしまう
- 何らかの目標に向けて焦っている
- 散財や性的逸脱行為がみられる
双極性障害(躁うつ病)の話し方に特徴はある?
双極性障害(躁うつ病)の話し方には、状態ごとにいくつかの特徴があります。
例えば、躁状態では話し方が速くなり、一つの話題から次の話題へと会話が飛ぶことが多いです。声のトーンは高くなり、興奮した口調になる傾向にあります。
うつ状態では、話し方が遅くなり声のトーンが低く抑えられます。言葉数も減り、全体的に無気力感が漂ったり返答が遅れたりします。言葉選びもネガティブな表現が増え、自分を下げる会話が増えることが特徴です。
双極性障害 (躁うつ病)の診断が遅れやすい理由

双極性障害(躁うつ病)は、症状が他の精神疾患と似ていること、躁状態が周囲に気付かれにくいこと、患者自身が症状を軽視することなどから、診断が遅れやすいといわれています。また、躁状態が比較的軽度の場合、うつ病と診断してしまい治療が遅れたり、症状が悪化したりすることもあります。
双極性障害 (躁うつ病)の診断が出るまでの受診回数
双極性障害患者211人に調査した結果によると、診断が出るまでの受診回数は20回以上が全体の49%をしめています。次に多いのは、2~5回目で17%となっており、状態の出方により診断が遅れてしまうことが伺えます。
また、最初の診断ではうつ病と診断された人は57%と半数を超える結果に。理由としては、うつ状態の時に受診をする人が多いため、躁状態が見つかりにくいことが関係しているとされています。
参考
・第1回 双極性障害(躁うつ病)と診断されるまで|すまいるナビゲーター
双極性障害 (躁うつ病)の診断で間違えやすい精神病

双極性障害(躁うつ病)は、さまざまな精神疾患と症状が重なるため、診断を間違えられてしまうことがあります。
ここでは、双極性障害と間違えやすい代表的な精神病について解説します。
うつ病
うつ病は、気分が強く落ち込み憂うつ気分が続く精神疾患です。双極性障害(躁うつ病)で起こるうつ状態と同様の症状がみられるため、うつ状態が長かったり躁状態が軽度であったりする場合に誤診が起こりやすくなります。
双極性障害との違いは、気分が高揚する瞬間がないことです。常に気分が下がり悲しい気持ちが継続することで、登校拒否や休職など私生活に影響を及ぼします。
パーソナリティ障害
パーソナリティ障害は、感情の起伏が激しく思考が両極端だったり、怒りの抑制ができなかったりする精神疾患です。躁状態でみられるイライラや衝動的な行動と症状が似ており、判断が難しい場合があるといわれています。
双極性障害との違いは発症原因です。双極性障害は遺伝や脳の機能異常が関係しているとされる一方で、パーソナリティ障害は幼少期のトラウマやストレスが原因といわれています。
統合失調症
統合失調症は、考えがまとまらなくなり幻聴や妄想が起こる精神疾患です。自分の中では、幻聴や妄想が本当のものだと思っているため、周囲の人間とトラブルになったり感情が暴走したりします。
双極性障害でみられる、「自分には特殊能力がある」「何者かに狙われている」「存在してはいけないのではないか」などの妄想が、統合失調症の症状と重なるため間違って診断される場合があります。
不安障害
不安障害とは、強い不安や緊張によりパニック発作が出てしまう精神疾患のことです。症状は、「人混みが耐えられず過呼吸になる」「人前で緊張して話せなくなる」「全ての事柄を考えすぎてしまい強い不安に襲われる」などさまざまです。
双極性障害の混合状態では、落ち込みと興奮が同時にやってくることで強い不安が引き起こされ、不安障害と似た症状がみられます。
心身症
心身症は、ストレスによって何らかの身体的不調が引き起こされる疾患です。
症状は多岐に渡りますが、代表的なものとしては頭痛や腹部の違和感、吐き気、倦怠感があげられ、場合によっては双極性障害と間違えられてしまいます。
双極性障害 (躁うつ病)の症状は、診断されるどのくらい前からみられた?

双極性障害の患者211人に行った調査結果によると、思い当たる症状が1年以上前からあったと答えた人は全体の79%となりました。
211人中64人は、10年以上前からと回答し、次に多いのは5年~10年未満で41人となっています。
双極性障害は、約100人に1人は一生のうちに1度はかかる疾患といわれています。自覚のないうちに発症していたケースもあるので、症状が気になる場合は心療内科や精神科に相談してみましょう。
参考
・第1回 双極性障害(躁うつ病)と診断されるまで|すまいるナビゲーター
・双極性障害(躁うつ病)とつきあうために|日本うつ病学会 双極性障害委員会
双極性障害 (躁うつ病)の診断方法

双極性障害(躁うつ病)の診断では、米国精神医学会が発行しているDSM-5の診断基準に基づき、うつ状態と躁状態を診断します。
また、躁状態は2タイプに分けられ、症状により私生活に支障を与えていたり入院が必要であったりする場合は「躁状態」、他人からみても明らかな症状が4日以上続いているが支障がない場合は「軽躁状態」と診断されます。
双極性障害 (躁うつ病)と診断を受けた際に大切なこと

ここでは、双極性障害 (躁うつ病)の診断を受けた際に知っておくべき3つの大切なことを解説します。
薬を途中でやめない
処方された薬は、期間と容量を守りしっかりと飲み続けるようにしましょう。
薬を途中でやめると、症状が悪化したり再発につながったりする可能性があります。また、放置すると再発までの間隔が短くなり、繰り返し発症するようになるため、根気強く治療を継続していくことが大切です。
職場復帰は慎重に行う
復職する際は、ゆっくりと時間をかけて体を慣らしていきましょう。いきなり頑張り過ぎてしまうと、身体に大きな負担がかかり悪化してしまう可能性があります。
症状が安定したと感じる際でも、医師と相談しながら適切なタイミングと環境で復職をしていくと良いです。
何かあったらすぐに相談する
何か問題があった場合は、再発や症状悪化を防ぐためにも担当医へ相談しましょう。
また、身近な人に事情を知ってもらうことで、症状に対するサポートや理解を得られるかもしれません。話すだけでも心が楽になるので、信頼できる人に打ち明けることもおすすめです。
双極性障害 (躁うつ病)の疑いがある場合は、心療内科うるおいクリニックにご相談ください
うるおいクリニックでは、双極性障害(躁うつ病)の治療に対応しています。
治療では、薬物療法や心理療法のほかにも、脳に直接働きかけるTMS治療を採用。幅広い治療を導入することで、患者様1人ひとりに合わせたアプローチを可能にしています。
「なんとなく体が重い気がする」「微妙な体調不良で病院に行くべきか迷っている」などの些細な症状にも対応しているので、お悩みを抱えている方はお気軽にご相談ください。
よくある質問
双極性障害 (躁うつ病)の症状に周期はありますか
双極性障害(躁うつ病)の症状には周期がありますが、症状の周期や頻度は個人差が大きく、特定のパターンがないケースもみられます。
双極性障害 (躁うつ病)は治りますか
双極性障害(躁うつ病)は慢性疾患ですが、適切な治療と管理により症状のコントロールが可能です。治療を通して生活の質向上を目指せるので、ぜひ一度ご相談ください。
![【公式】うるおいクリニック | 新宿の心療内科・精神科[東京新宿駅徒歩3分] 【公式】うるおいクリニック | 新宿の心療内科・精神科[東京新宿駅徒歩3分]](https://uruoi-clinic.jp/wp-content/uploads/2023/11/8bc62af8e5a38dea020696820b40417f-e1700099373323.png?1719419206)

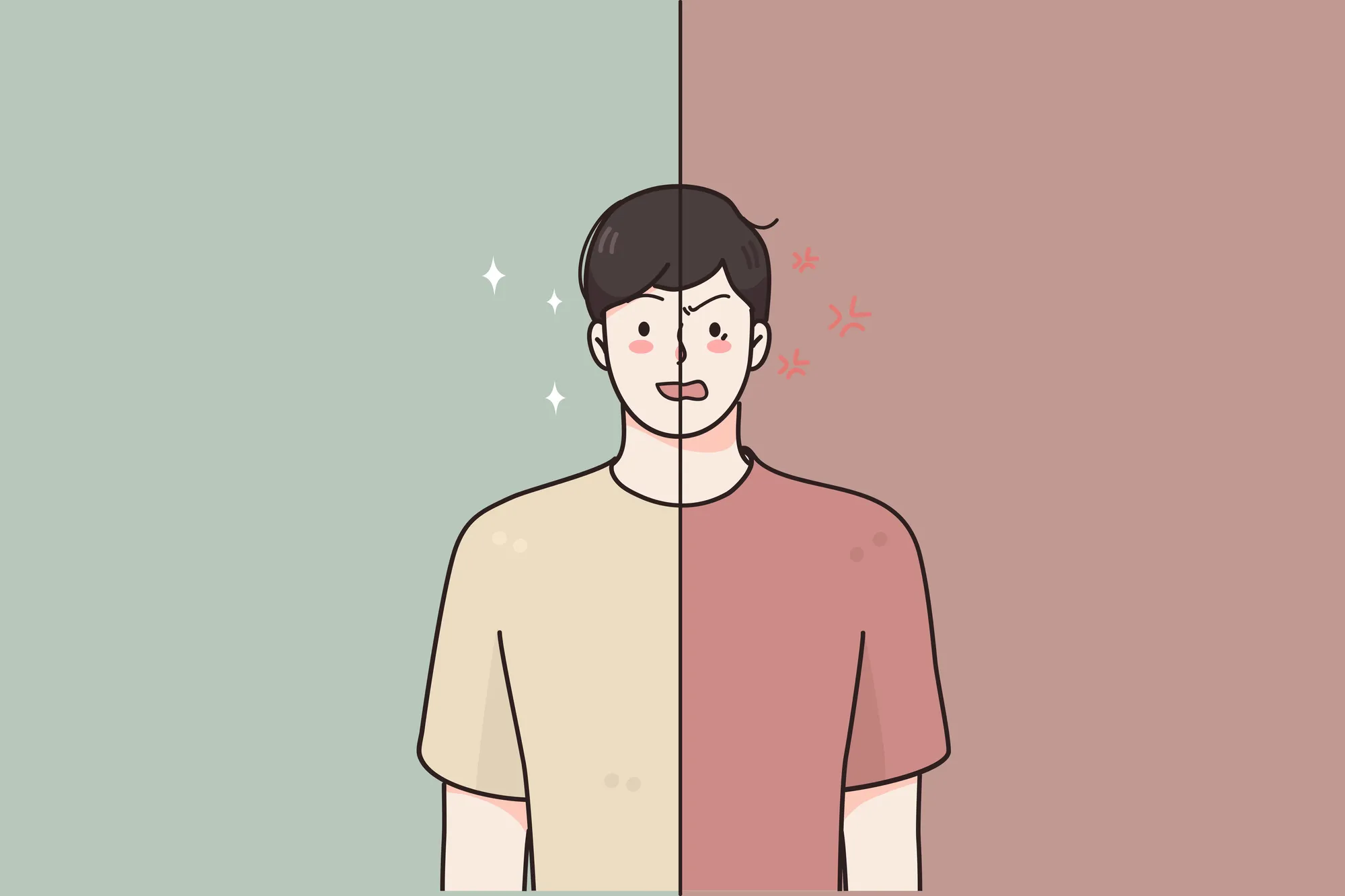

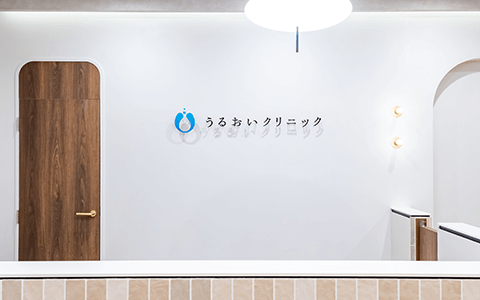


![【公式】うるおいクリニック | 新宿の心療内科・精神科[東京新宿駅徒歩3分] 【公式】うるおいクリニック | 新宿の心療内科・精神科[東京新宿駅徒歩3分]](https://uruoi-clinic.jp/wp-content/uploads/2023/12/b5646d26d4ad2933da6d291c7703357b.png?1719419207)