仕事や離婚など特定のストレスにより発症する適応障害は、誰でもなり得る疾患です。
再発リスクも高いため症状について正しく知っておき、事前に対策を講じることが大切ですが、
「どんなことが原因で適応障害は発症するのか」
「突然涙が出る症状は適応障害なのか」
と様々な疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、適応障害について知りたい方向けに、原因や症状から治療法まで気になる疑問を含めて丸ごと解説します。記事を通して、適応障害に対する理解を深められるので、ぜひ参考にしてみてください。
目次
適応障害とは

適応障害とは、本人にとって耐え難い特定のストレスが原因となり、心身に不調をもたらす精神疾患です。例えば、仕事でのプレッシャーや人間関係の不和、家庭内問題によるストレスが大きくなると発症し、抑うつ気分や不眠、焦燥感、疲労感などの症状が伴います。
行動面でも
「急に引きこもる」
「コミュニケーションが上手くいかなくなる」
といった社会的孤立を招く可能性があるようです。
ストレスの解消に伴い、徐々に症状は落ち着いていきますが、中々ストレス源から離れられない場合は悪化や慢性化リスクが懸念されます。
また、適応障害としてストレス反応が強く出ることから、仕事を休みがちになったり無断欠勤が増えたりする可能性もあるので、症状に気付いた段階で早めに対処しましょう。
適応障害はストレスバランスが崩れることで起こる
適応障害は、持続的なストレスにより心身に負荷がかかり、対処できなくなることで起こるといわれています。
人は生活の中で様々なストレスを受けますが、通常であれば体の働きにより適切に処理されます。しかし、ストレスが多かったり長時間続いたりすると、心身のバランスが崩れて適応障害を引き起こすのです。
例えば、仕事でプレッシャーを感じ続けている場合、精神的な疲労が限界を超えると適応障害として現れる可能性が高まります。また、ストレス耐性が低い場合も精神的な疲労が蓄積する原因となり、適応障害の症状を引き起こすと考えられています。
適応障害の原因

適応障害の原因には、外的要因と内的要因があり、また、それらが複雑に絡み合っているケースもあります。外的要因としては、生活環境や仕事での変化、対人関係問題などがあげられます。内的要因としては、性格やストレス耐性が関連しており、生じた出来事に対する個々の受け止め方次第で発症に至るようです。そのため、同じようなストレスを受けた場合でも、適応障害を発症する人としない人が存在します。
適応障害の原因となる外的要因の事例
- 上司からのパワハラ
- 自分では対応しきれないほどの仕事量を任される
- 引っ越し先で地域に馴染めない
- 身近な人との別れ
- ママ友トラブル
- 結婚、出産等の大きなライフイベント
- 入学・進学による環境変化
適応障害になり得る外的要因は人によって様々ですが、職場でのストレスや対人関係トラブル、大きな環境変化はきっかけになりやすいといわれています。
また、
「引っ越し先で地域に馴染めない」
「グループ内でいじめを受けている」
「悩みの相談先がない」
など孤立やサポートを受けられないと感じる環境も、適応障害を引き起こすようです。
適応障害の原因となる内的要因の事例
- 悲観的に考えやすい
- 一つひとつの出来事に敏感に反応してしまう
- 完璧主義者
- 自己肯定感が低い
- 責任感が強い
- 感情表現が苦手
- ストレスを溜め込みがち
適応障害には、性格や元々持っている性質も大きく関わります。
例えば、悲観的に考えやすい人や敏感に反応してしまう人の場合、楽観的な人に比べてストレスを感じる機会が増えます。完璧主義や自己肯定感が低い人も、問題を自己解決しようと自分を追い込みすぎるため適応障害になりやすいといわれています。
また、ストレス発散法を知らなかったり感情表現が苦手だったりする人は、ストレスを溜め込んでしまうことから発症に至るようです。
下記記事では、適応障害になりやすい人に多い環境や性格について詳しく解説しています。併せてチェックしてみてください。
適応障害の主な症状
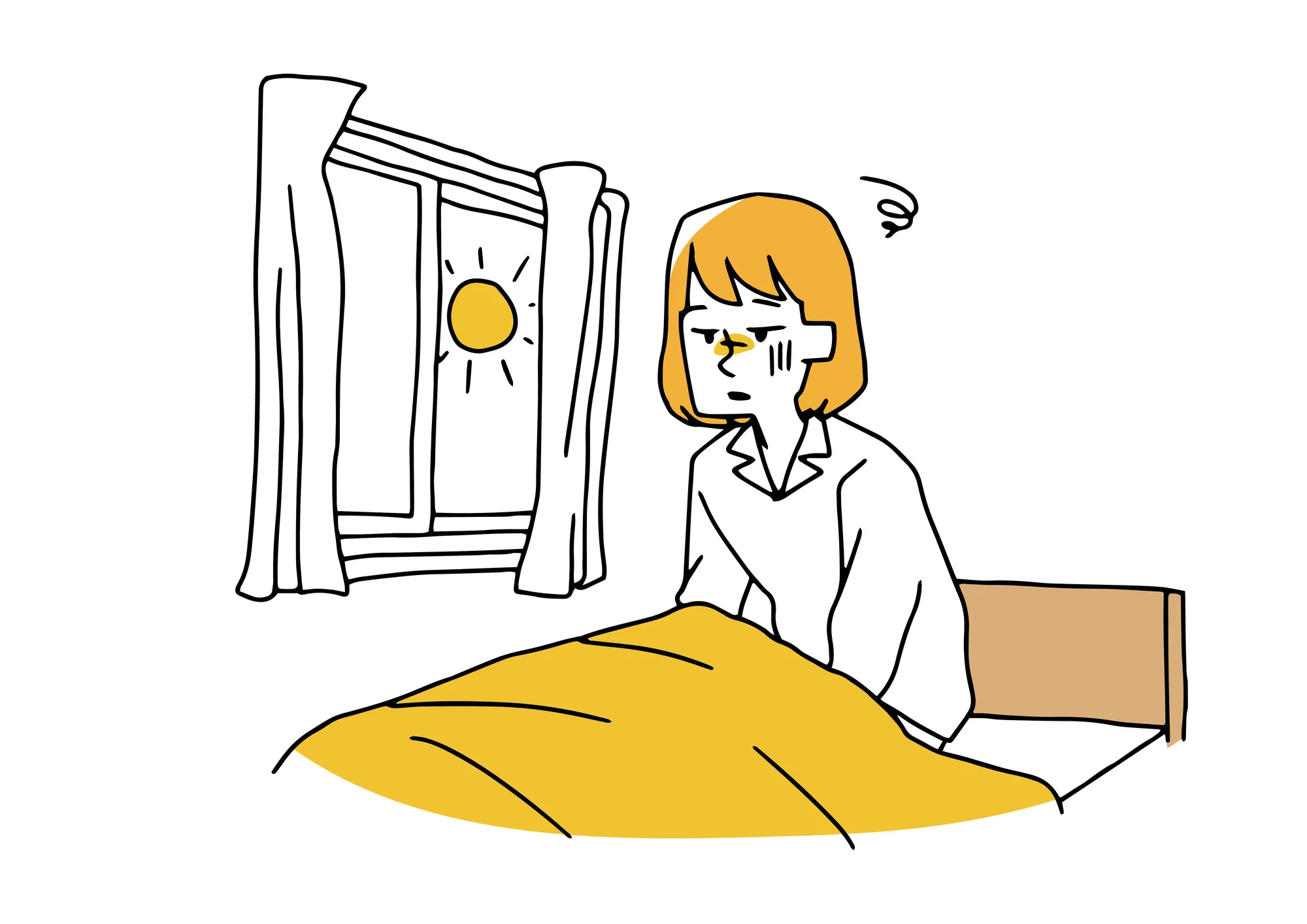
適応障害は、抑うつ気分などの精神障害以外にも、不眠・動悸といった身体症状が現れることが特徴です。また、社会的問題行動として人間関係のト ラブルや無断欠勤が増えるケースもあります。
症状は幅広く個人差も大きいので、「精神症状」「身体症状」「社会的問題行動」でみられる主な症状についてみていきましょう。
適応障害の症状①精神症状
精神症状では、主に抑うつ気分や不安、焦り、過度の緊張などがみられます。症状はストレス源に触れた時に起こり、精神的負荷が大きいほど症状が強く出るといわれています。
例えば、仕事が原因となっている場合、出社準備をしている際に症状が現れたり、仕事のことを考えると気分が悪くなったりします。突然涙が止まらなくなる、絶望感に襲われるなどの症状に悩まされるケースもあり、感情のコントロールが難しくなるようです。
また、症状による自己否定感から、
「周りと比べて自分は劣っている」
「他人の期待に応えられずつらい」
と感じることもあります。
適応障害の症状②身体症状
身体症状としては、不眠、慢性的な疲労感・倦怠感、頭痛、動悸、めまいなど様々な症状が現れます。症状は精神的なストレスによって現れるものであり、ストレス源の解消に伴い徐々に改善されますが、不眠や食欲不振の影響で体を回復できないと治りづらくなるようです。
また、症状の現れ方はその日の体調や個々の性質によって異なり、仕事がある日は起きられない起床困難や中々回復しない頭重に悩まされるケースもあります。
適応障害の症状③社会的問題行動
社会的問題行動としては、喧嘩や引きこもり、人間関係の断絶などが該当します。
症状は、イライラや感情の不安定さが顕著になることで起こるとされ、周囲の人とコミュニケーションが取れなくなったり衝突が増えたりするようです。
問題行動が悪化すると、今まで通りの社会生活が送れなくなり、孤立感や自己否定感が強まると考えられています。適応障害自体の慢性化リスクを高める要因になり得るため、何かおかしいと指摘されたり、違和感を覚えたりしたタイミングで治療を受けることが大切です。
下記記事では、適応障害の症状やストレスサインについて詳しく解説しています。併せてチェックしてみてください。
適応障害の症状例

適応障害の現れ方は個人差がありますが、ストレス源自体を避けたりストレスからくる不安を考えすぎたりする症状は出やすいといわれています。
以下では、主な症状例としてあげられる
「仕事に行きたくなくなる」
「強い不安から眠れない」
「対人トラブルなどの問題行動が増える」
についてそれぞれ解説していきます。
仕事に行きたくなくなる
適応障害の原因が仕事の場合、仕事を考えると不安や恐怖を感じたり、出社自体ができなくなったりする症状が現れる傾向にあります。また、ストレスやプレッシャーから心身が疲弊し、強い倦怠感を感じて仕事に行く行為が苦痛になります。
出社準備はできたとしても、欠勤や遅刻、無断欠勤も増えるため、仕事に行かないことが段々と当たり前になり意欲が低下していくようです。また、職場では集中力が続かなかったり小さなミスが増えたりと、作業効率が悪くなるといわれています。
強い不安から眠れない
ストレス源に対して強い不安を持っていると、常に頭の中で考えてしまい寝ようとしても眠れなくなったり途中で起きてしまったりするようです。
不眠症状が続くと、体がリラックス状態に入りづらくなったり、起床時の倦怠感や脳のリセットがされなくなったりして、日中に影響を及ぼすとも考えられています。また、睡眠不足により疲労がどんどん蓄積されると、不安やイライラが強まり回復の妨げになるといわれています。
対人トラブルなどの問題行動が増える
ストレスが増すと感情のコントロールが難しくなり、喧嘩などの問題行動を起こしやすくなるようです。小さな出来事に過剰に反応するため、同僚のちょっとした発言に敏感になったり家庭内での揉め事が増えたりします。
頻発する対人トラブルにより
「自分は価値のないダメな人間だ」
「誰かを傷つけるから人と関わってはいけない」
と感じてしまい、引きこもりがちになるケースもあるといわれています。
適応障害をセルフチェック診断リストで確認してみよう

適応障害の疑いがある場合、まずはセルフチェック診断リストで症状を確認しましょう。自分自身で適応障害の症状を把握しておくことで、早期の対処が可能になります。
適応障害のセルフチェック診断テスト
下記のセルフチェック診断リストを参考に、自身の症状が適応障害に当てはまるかチェックしてみましょう。
- 抑うつ気分や不安
- イライラ、焦り、緊張
- 計画を立てることが難しいと感じる
- 暴飲暴食がみられる
- 無断欠勤などの問題行動が増える
- ストレスを感じると呼吸が浅くなって息苦しさを覚える
- 発汗、めまいがある
- 仕事に行く日になると異常なほど憂うつな気持ちになる
これらの項目に当てはまる場合、適応障害の可能性があります。セルフチェック診断リストでは適応障害の断定はできないので、心当たりがある方は病院へ受診しましょう。
下記記事では、適応障害のセルフチェック診断や実例について、より詳しく解説しています。併せてご確認ください。
適応障害の診断基準
病院で診断をする際は、
「他の精神疾患に当てはまらないか」
「明確なストレス源があるか」
「ストレスがなくなると症状は消えるか」
などをチェックすることが一般的です。
以下では、日本精神学会で定めている適応障害の診断基準をご紹介します。A~Eに全て当てはまる場合、適応障害に該当するので病院へ受診しましょう。
- A:
一つの明確なストレス源に対して反応し、ストレスが生じてから3カ月以内に症状がみられた - B:
(1)性格や環境などを考慮しても、ストレス源に対して不釣り合いなほどの強い苦痛を感じる
(2)社会生活や仕事を送る上で問題が生じるほどの症状に悩まされている - C:
ストレスによる症状は他の精神疾患に該当しない - D:
症状は、家族や大切な人との死別反応とは無関係に起こっている - E:
ストレス源がなくなると症状は6カ月以内に収まる
参考
日本における「適応障害」患者数の増加ーメンバーシップ型雇用からの考察ー(社会政策学会誌『社会政策』第12巻第2号)|池田 朝彦
適応障害になりやすい人

適応障害は、個々のストレス耐性や性格などが関わってくるため、同じストレス環境にいる場合でも発症する人といない人が存在します。
例えば、感情を表に出さず1人で抱え込んでしまう人は、ストレスを適切に発散できている人に比べて適応障害を発症しやすいようです。
以下では、適応障害になりやすい人としてあげられる
「ストレスを溜めこみがちな人」
「責任感が強く頼みごとを断れない人」
について解説するので、それぞれの特徴をみていきましょう。
適応障害になりやすい人①ストレスを溜めこみがちな人
ストレスを溜めこみがちな人は、問題が生じても他人へ相談や助けを求められない傾向にあります。1人で抱え込んでしまった結果、ストレスが解消されないまま精神的疲労が徐々に蓄積されていきます。
また、問題が大きくなり取り返しがつかなくなると、自分ではどうしようもできず精神的に押しつぶされてしまうようです。このように、ストレスや不安を共有する機会を作らず何とかしようとするケースが多いため、適応障害を引き起こす原因になるといわれています。
適応障害になりやすい人②責任感が強く頼みごとを断れない人
責任感が強く頼みごとを断れない人は、自身に課された役割や責任を強く意識しすぎるあまり、キャパオーバーでも頼み事を引き受けてしまう傾向にあります。
また、周囲への配慮を優先したり、期待に応えようと無理をしすぎたりするため、いつのまにかストレスが蓄積している人が多いようです。
自己管理も疎かになりがちで、疲れているのに自分を犠牲にして休息をとらないことが適応障害を引き起こすともいわれています。
適応障害の治療法

適応障害の治療法では、「認知行動療法」「環境調整」「薬物療法」が用いられるケースが一般的です。認知行動療法では思考自体にアプローチ、環境調整では環境を変えることでストレスを減らす、薬物療法では症状の改善とそれぞれ異なる役割を持っています。
主に環境調整を基本として行うケースが多いですが、他の治療との併用により効果が高まるといわれているので、それぞれの特徴やアプローチ法について知っておきましょう。
適応障害の治療法①認知行動療法
認知行動療法は、思考自体にアプローチすることで、ストレスに対する考え方を変えていく治療法です。
適応障害になると、症状を引き起こすストレスに触れた際に、通常であれば気にならない些細な出来事に対しても強い苦痛を感じる傾向にあります。認知行動療法では、ネガティブに捉えてしまう原因を深掘りし、違う捉え方ができるようにしたり行動を振り返って実際は大丈夫と認識させたりします。
適応障害の治療法②環境調整
特定の問題により生じる適応障害の場合、環境調整を通してストレス源から距離をとることが大切です。
例えば、過剰な仕事量からストレスを感じているケースでは、業務量の調整やタスク分担、時短勤務などの環境調整を行います。家庭内でのストレスが大きい際は、家族と改めてコミュニケーションをとったり、1人になる時間を作ったりすることで、心身の休息と症状改善を促せます。
適応障害の治療法③薬物療法
薬物療法は、不安や抑うつ気分、不眠など症状に合わせて服用されるケースがあります。
例えば、強い抑うつ気分で何も手につかなくなっている場合、SSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)などの抗うつ薬を用いることで症状の軽減を図れます。不安から眠れない場合は睡眠導入剤が使われ、適切な睡眠により心身の疲労回復を促すようです。
薬の服用により症状軽減が期待できますが、あくまで症状に対するアプローチとなるため、症状を引き起こす根本原因の解消には環境調整などで現状を変えていくことが大切となります。
適応障害に使われる薬

先ほども説明したように、適応障害では症状ごとに異なる薬が用いられます。
以下では、主に使われる「睡眠導入剤」「SSRI・抗不安薬」がどのような症状に効果があるのか解説するので、自身の症状と照らし合わせながらチェックしてみてください。
睡眠導入剤が使われるケース
睡眠導入剤は、不安やストレスから寝つきが悪くなったり、途中で目が覚めてしまったり、眠れなくなったりしている場合に使用されます。
適応障害を治す際は休息が大切となりますが、適切な睡眠が取れていないと疲労が蓄積され、正常な判断ができない、不安感が強くなるなどの症状悪化リスクが増すようです。睡眠導入剤を用いて眠りを促すことで、しっかりと体が休まるため効果的な症状改善を図れます。
SSRI・抗不安薬が使われるケース
SSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)や抗不安薬は、強い不安や抑うつ症状に悩まされている時に使用されます。
例えば、不安から何も手につかない、些細な出来事に対しても過剰に反応してしまう、抑うつ気分で気力が出ないなど、強い不安や抑うつ症状がみられる際に使用されます。服用により症状緩和を促すことで、他の治療を前向きに取り組めるようになるため、必要に応じて併用すると良いです。
適応傷害の薬に興味がある方は、下記記事も併せてチェックしてみてください。
適応障害で休職はできる?

適応障害がつらく不調が治らない場合、休職をすることが可能です。
休職は、症状の度合いや個々の状況などを医師が総合的に判断した上で決定されます。仕事を一時的にセーブし体を休めることに専念すると、ストレスの原因となる環境から離れられて心身のリフレッシュを促せるでしょう。
適応障害の慢性化を防ぐためには休職も大切
適応障害で休職が必要と判断された場合、すみやかに職場へ伝えることが大切です。
特に仕事が原因となっている場合、休職を行わず今まで通り働き続けてしまうと、体調がさらに悪化したり、症状が長引いたりする可能性が高まります。職場が原因でない場合も、つらい気持ちを隠したまま無理をすると、よりストレスを受けやすくなるといわれています。
このような環境では、症状の慢性化リスクが高まり回復が遅くなってしまうので、早期に休職を決断するようにしましょう。
適応障害で休職するまでの流れ
一般的に適応障害で休職する際は、以下の流れに沿って休職手続きが行われます。
- ①病院へ受診
適応障害が疑われる場合は、精神科・心療内科へ相談しましょう。 - ②適応障害と診断
病院では診断基準などを基に、適応障害か否か判断します。 - ③診断書の作成依頼
休職を希望される際は、休職期間や治療内容などが書かれた診断書の作成依頼をお願いします。 - ④診断書を受け取り
診断書の受け取り後は、会社にて休職手続きを行います。
下記記事では、適応障害で休職する詳しい流れや職場への伝え方、休職明けの対応について解説しています。適応障害での休職手続きがイメージしやすくなるので、ぜひチェックにしてみてください。
適応障害で休職しないリスク
適応障害で休職せずに頑張り過ぎてしまうと、症状の悪化や職場でのパフォーマンス低下、社会的孤立などのリスクが高まります。
また、心身への負担が増えるため、うつ病などの他の精神疾患を併発する可能性もあり、最終的には働ける状態ではなくなったり、退職を余儀なくされたりする恐れも考えられます。
適応障害自体は、ストレス源から距離を置くことで回復を目指せる精神疾患ですので、休職が必要な場合は早めに会社へ相談し、体調を整えていくようにしましょう。
適応障害は何科に受診する?

適応障害で悩んだ際は、心療内科や精神科を受診するようにしましょう。
適応障害はストレスからくる疾患のため、心の健康を主に取り扱う精神科・心療内科を受診することで、根本解決や症状改善を目指せます。
自身の症状が適応障害なのか分からない場合も、「ストレスから調子が悪い」「なんとなくつらさがある」などメンタル面での不調がみられる際は精神科・心療内科で診てもらいましょう。
適応障害の受診目安
適応障害は、日常生活に支障をきたすような不安や抑うつ症状がみられたタイミングで早めに受診すると良いです。
例えば、仕事が嫌で朝起きるのがつらい、ストレスから集中力が続かない、ストレス源を考えると涙が出る症状は適応障害の可能性があります。不安から眠れなくなったり、食欲が減少したりする身体症状が現れるケースもあるので、心当たりがある際は一度相談してみましょう。
いち早く治療を始めると早期回復や再発防止につながるため、まだ頑張れると思わずつらいと感じたら医師や身近な人に助けを求めることが大切です。
適応障害の受診目安や放置するリスクについてより詳しく知りたい方は、下記記事をご確認ください。
適応障害に関するQ&A

ここでは、適応障害に関するQ&Aにお応えします。
休職に関する質問や症状の再発リスク、診断されても元気そうに見えるケースなどをまとめているので、ぜひ参考にしてみてください。
適応障害になると顔つきは変わる?
適応障害に関わらず、精神的なストレスが続くと顔つきが変わったようにみえる可能性があります。
例えば、強いストレスからくる睡眠不足や食欲の低下などに悩まされている場合、顔色が悪くなる、目の下にクマができる、目が虚ろになる、などの変化がみられるようです。
また、心の疲れが顔に出ることで、無表情に見えたり顔がこわばっているように見えたりする場合があります。
適応障害で休職できない場合はどうすればいい?
休職をしても職場の理解が得られない場合は、医師に職場に向けた症状説明をお願いしたり、業務内容の変更などの別の措置を依頼したりすると良いです。
例えば、リモートワークやフレックス制度の活用など、自身がストレスを感じにくくなる働き方の提案により、会社が受け入れやすくなる可能性があります。職場と関わること自体がつらい際は、退職なども視野に入れると良いかもしれません。
適応障害は放置していいの?
適応障害は放置してはいけません。つらいまま何も対処しないと、症状の長期化や他の精神疾患を併発する恐れがあります。また、不安や抑うつ気分が強まることから仕事や人間関係に悪影響を及ぼしたり、引きこもりに発展したりする可能性も考えられます。
適応障害は、環境を整え十分に休息をとることで回復を目指せるので、
「これくらい平気」
「まだ頑張れる」
と無理をせず治療を受けるようにしましょう。
元気そうに見えても適応障害と指摘されるケースはある?
適応障害の症状は、ストレス源に触れている時に現れる傾向にあるため、
「休日は元気に活動できる」
「うつ病のように常に落ち込んではいない」
などの理由から一見元気そうに見えても適応障害と診断されるケースはあります。
また、仕事のストレスや人間関係の悩みを抱えていても、感情に蓋をして明るく振る舞っている可能性もあるため、体調に違和感を覚えた際は医師に相談することが大切です。
適応障害は一度治れば再発しないの?
適応障害が一度治ったとしても、何らかの理由で再発する可能性があります。例えば、再び大きなストレスにさらされたり、新たな環境変化が起こったりした場合、同様の症状に悩まされる人もいるようです。
完治後も、環境調整やストレス管理を意識し、なるべく負担のかからない生活を送ることが大切なので、無理をせず少しずつ日常を取り戻していきましょう。
適応障害でお悩みの方は新宿うるおいこころのクリニックへご相談ください
「適応障害の症状がつらい」とお悩みの方は、新宿うるおいこころのクリニックへご相談ください。
ひどい適応障害の症状は、薬物療法により回復を目指せるといわれており、早期の相談と治療により悪化を防げます。新宿うるおいこころのクリニックでは、臨床心理士、公認心理士在籍のカウンセリングも並行して行えるので、ストレス源を明確にした上で悩みに合わせたサポートの提供が可能です。
他の精神疾患を併発している場合でも、症状に合わせた治療提案が可能ですので、どうぞお気軽にご相談ください。
よくある質問
適応障害は薬を使わずに治せますか?
適応障害はストレス源の解消が大切となるため、薬を使わずに治すことも可能です。しかし。抑うつ気分が強く表れている場合や、不安から日常生活に大きな支障をきたしている場合など、薬物療法が必要なケースもあることを理解しておきましょう。
適応障害は甘えですか?
適応障害は「甘え」ではありません。症状には個人差があり、比較的元気に過ごせる時もあるため、周囲から理解されにくいこともありますが、精神疾患の一つであり適切な治療が大切となります。
![【公式】新宿うるおいこころのクリニック | 新宿の心療内科・精神科[東京新宿駅徒歩3分]](https://uruoi-clinic.jp/wp-content/themes/uruoi/assets/img/logo-b.svg)








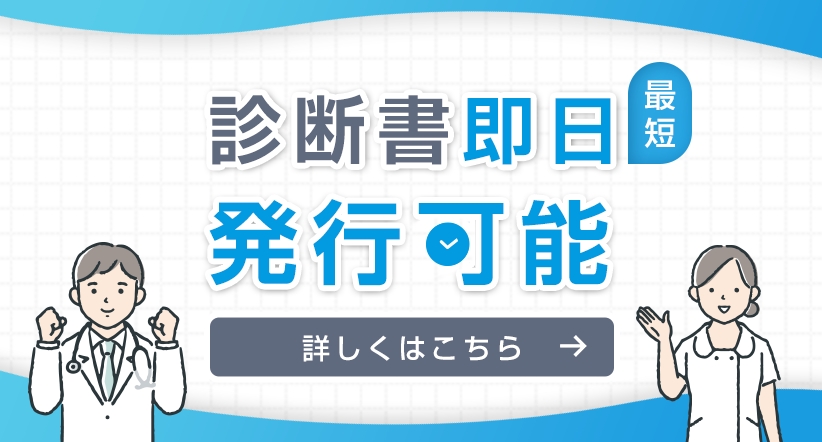




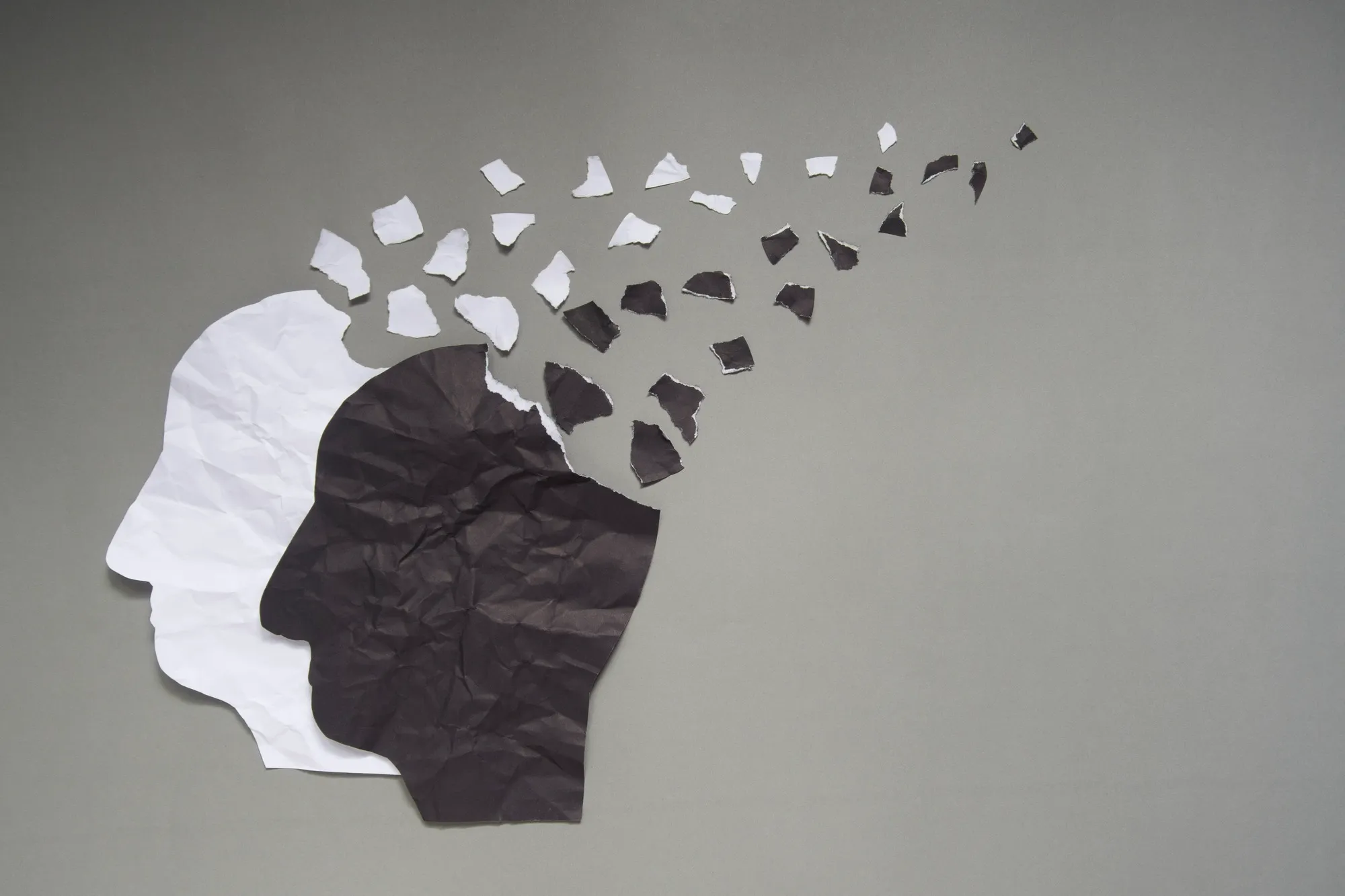



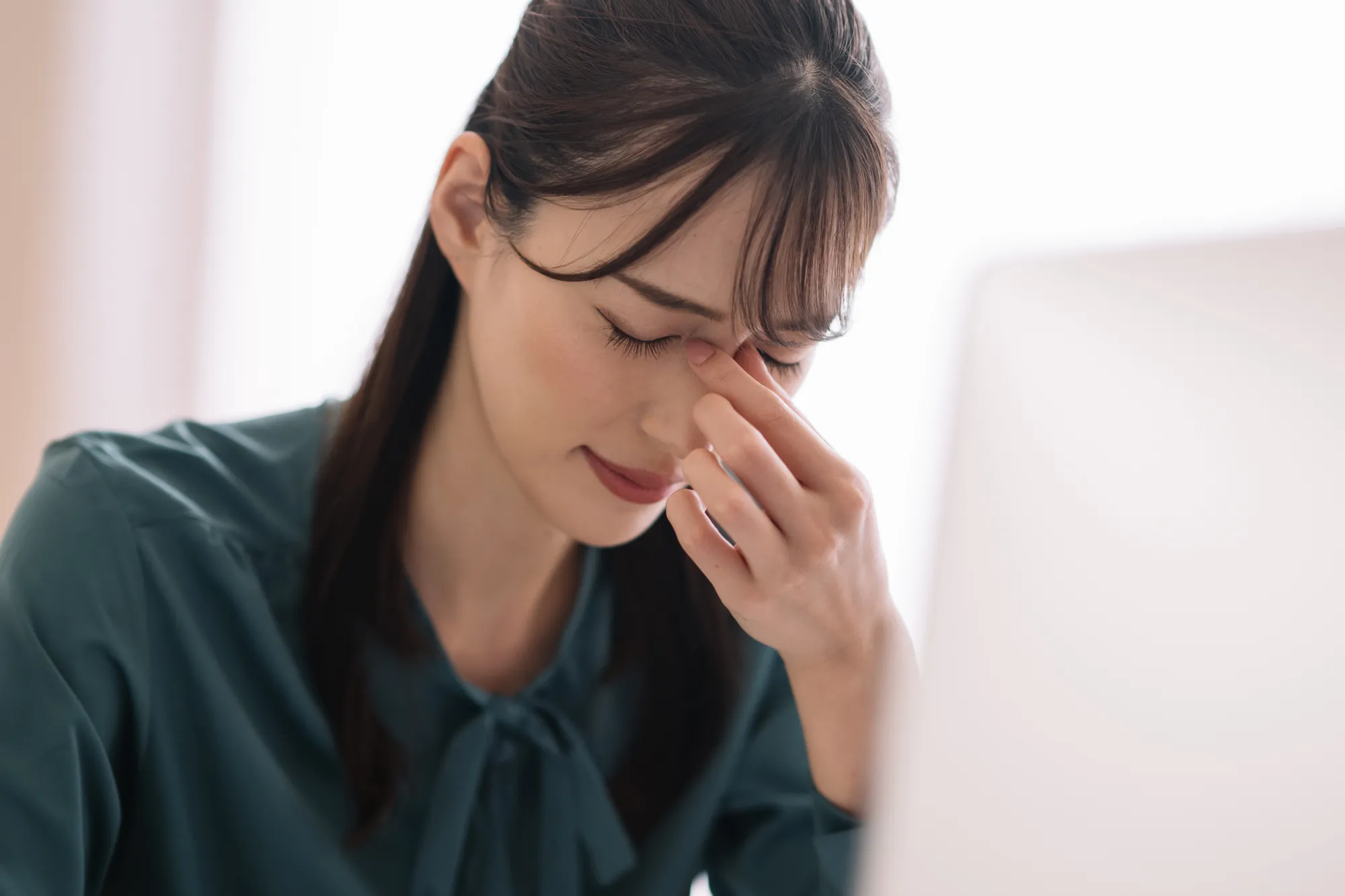





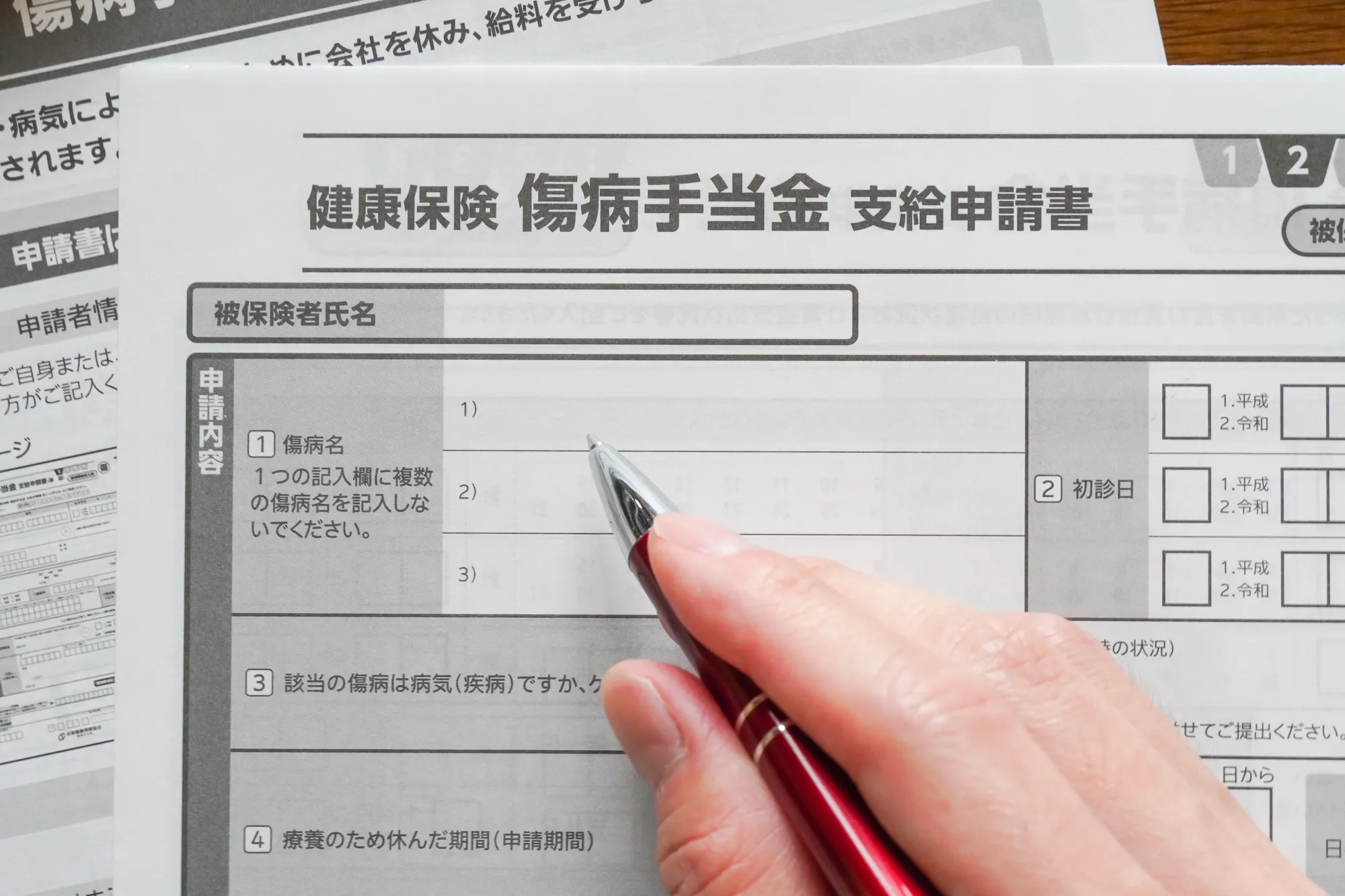




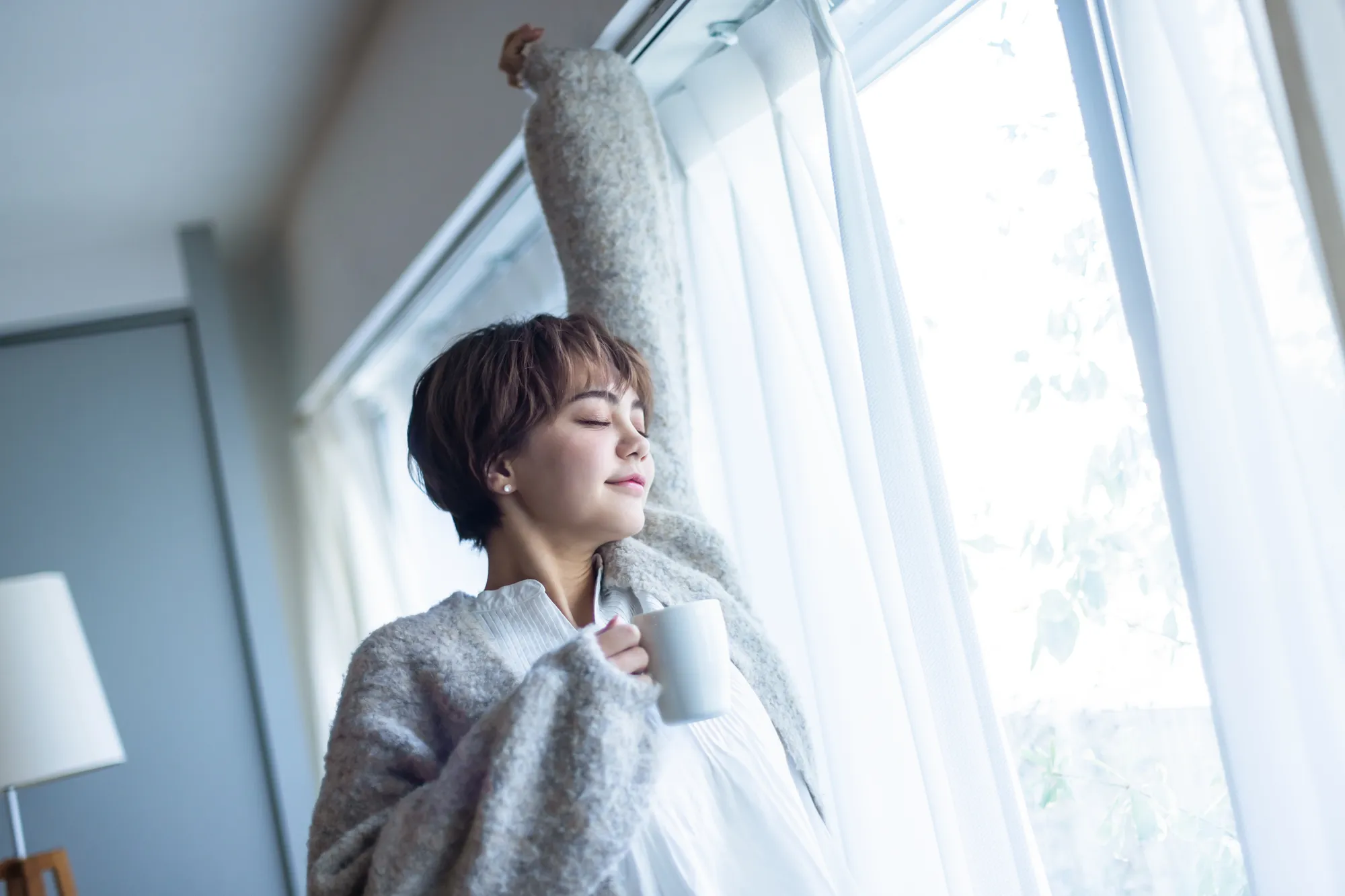
![【公式】新宿うるおいこころのクリニック | 新宿の心療内科・精神科[東京新宿駅徒歩3分]](https://uruoi-clinic.jp/wp-content/themes/uruoi/assets/img/logo.webp)




