「眠っても疲れが取れない」
「何科を受診すればいいんだろう…」
など、睡眠に関する疑問や悩みを抱える人は多いものです。
こうした症状の裏には、ストレスや生活習慣の乱れ、あるいは睡眠障害と呼ばれる疾患が隠れていることがあります。しかし、適切な治療を受けることで睡眠の質を改善し、日常生活の快適さを取り戻すことは可能です。
この記事では、睡眠障害の代表的な疾患を紹介し、病院に行く場合は、病名、症状に応じてそれぞれ何科を受診すればいいかを解説します。さらに、どのようなタイミングで病院を受診すべきかについてもご案内します。睡眠に関するお悩みがある方は、ぜひ参考にしてみてください。質の高い睡眠を目指す第一歩を踏み出しましょう。
目次
睡眠障害とは睡眠に関連した病気の総称

睡眠障害とは、眠ることに関わる問題が生じる疾患の総称です。現代の生活環境や働き方の変化により、十分な睡眠を確保するのが難しくなる中、多くの人が何らかの睡眠障害を経験しています。
睡眠障害を発症すると、
「眠りが浅い」
「眠りにつけない」
「日中に異常な眠気がある」
といった症状として現れます。その原因は、ストレスや生活習慣の乱れ、ホルモンバランスの変化、さらには身体的な疾患などさまざまです。
こうした睡眠障害を放置すると、心身の健康に悪影響を及ぼし、集中力の低下や免疫力の低下、さらには生活習慣病のリスクが高まることがあります。
睡眠障害に該当する代表的な疾患の一覧
睡眠障害には、さまざまな疾患が含まれており、それぞれ異なる症状や原因を持ちます。以下の表では、代表的な睡眠障害について、主な症状と原因をまとめています。
- 主な症状:
寝つきが悪い、夜中に何度も目が覚める - 原因:
ストレス、生活習慣の乱れ、心理的要因
- 主な症状:
昼間の耐えられない眠気、突然の眠り - 原因:
脳の神経伝達物質の異常、遺伝的要因
- 主な症状:
生活リズムのずれ、時差ぼけのような症状 - 原因:
不規則な生活、光や食事の影響
- 主な症状:
いびき、呼吸停止、日中の強い眠気 - 原因:
肥満、慢性的な鼻づまり、骨格の特徴
- 主な症状:
脚や下半身のむずむず感、不快感で眠れない - 原因:
鉄分不足、遺伝、神経の異常
- 主な症状:
夢遊病、夜驚症、悪夢 - 原因:
発達段階、ストレス、神経系の問題
こうした睡眠障害は、放置すると健康や生活の質に大きな影響を与える可能性があります。そのため、気になる症状がある場合は、早めに専門医を受診し、正確な診断を受けることが重要です。
参考
睡眠障害とは -睡眠障害の種類-(日本睡眠学会)|井上雄一
睡眠障害は何科の病院で診てもらえる?代表的な疾患と対応する診療科を解説

睡眠障害の治療には疾患ごとに適した診療科の受診が重要です。不眠症、過眠症、睡眠時無呼吸症候群など、代表的な疾患と対応する診療科をわかりやすく解説します。
不眠症の場合:内科・精神科・心療内科
不眠症は、「眠れない」「途中で目が覚める」「眠りが浅い」などの症状が特徴です。原因は、ストレスや生活習慣、精神的・身体的な問題など多岐にわたります。
軽度の場合は、内科で薬剤治療などを組み合わせながら、睡眠習慣の改善をするのが一般的です。全国的に内科は数が多く、気軽に相談しやすい点がメリットです。
一方、精神的な不調が原因の場合は、精神科や心療内科の受診がおすすめです。これらの科では、カウンセリングや認知行動療法、薬物療法によって心のケアを行い、不眠の根本原因にアプローチします。
参考
不眠症は何科を受診すべき?内科でもいいのか解説|病院に行くタイミングも紹介|起立性調節障害改善協会
過眠症の場合:脳神経内科
過眠症は、十分な睡眠時間を確保していても、日中に異常なほど強い眠気が続く症状が特徴です。この症状は、脳の睡眠と覚醒を調節する機能の異常が原因とされ、特に「ナルコレプシー」が代表的な疾患として挙げられます。
過眠症が疑われる場合は、脳神経内科を受診するのが適切でしょう。脳神経内科では、脳波検査や睡眠ポリグラフ検査などの専門的な検査を行い、症状の原因を詳しく調べます。
治療では、日中の眠気を軽減するための薬物療法や、睡眠と覚醒のバランスを整えるための生活習慣の改善指導が行われます。適切な診断と治療を受けることで、日常生活の質を向上させることが期待できるでしょう。
参考
中枢性過眠症 | 国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所睡眠・覚醒障害研究部
概日リズム睡眠障害の場合:精神科・心療内科
概日リズム睡眠障害は、体内時計の機能が乱れ、睡眠と覚醒のリズムが一般的な生活時間に適応できなくなる疾患です。具体的には、夜型の生活が続く「睡眠相後退症候群」や、シフト勤務が原因で起こる「交代勤務障害」などが代表例として挙げられます。
このような症状がある場合は、精神科や心療内科を受診するのが適切です。
これらの診療科では、体内時計を整えるための光療法やメラトニン製剤の使用、必要に応じてビタミンB12を用いる治療が行われます。また、生活習慣の改善指導を通じて、体を理想的な睡眠パターンに慣らしていくアプローチも取り入れられます。
原因に応じた治療を行うことで、日常生活への影響を最小限に抑えることが期待できるでしょう。
参考
概日リズム睡眠・覚醒障害(CRSWD) | 国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所睡眠・覚醒障害研究部
睡眠時無呼吸症候群(SAS)の場合:いびき外来・耳鼻咽喉科・呼吸器内科
睡眠時無呼吸症候群(SAS)は、睡眠中に呼吸が繰り返し止まることで、いびきや日中の強い眠気、集中力の低下などが生じる疾患です。主な原因として、肥満や扁桃腺の肥大、鼻の通りが悪いことなどが挙げられます。
睡眠時無呼吸症候群(SAS)が疑われる場合は、いびき外来や耳鼻咽喉科、呼吸器内科を受診するのが適切です。これらの診療科では、無呼吸の頻度や重症度を評価します。そのうえで、症状に応じた治療が選択され、マウスピースの装着、肥満改善指導、CPAP(持続陽圧呼吸療法)といったアプローチが用いられます。
但し、マウスピース治療やCPAP療法といった治療法は対症療法であり、症状の緩和は望めますが、別途、肥満改善やいびきレーザー治療といった睡眠時無呼吸症候群(SAS)の原因となっている要因を取り除く根本的な治療が必要です。
これらの検査や治療は専門的な設備が必要ですが、経験豊富な医師が対応するクリニックであれば安心して治療を受けることができます。睡眠の質の改善も期待できるでしょう。
<睡眠時無呼吸症候群(SAS)の治療ならいびき専門外来の「いびきメディカルクリニック」へ>
睡眠関連運動障害の場合:脳神経内科
睡眠関連運動障害は、睡眠中に無意識に手足が動いてしまう疾患で、むずむず脚症候群(レストレスレッグス症候群)や周期性四肢運動障害が代表例です。これらの症状は、睡眠の質を大きく低下させる要因となります。
この疾患の原因は神経系の異常と考えられているため、脳神経内科での相談が適切です。脳神経内科では、むずむず感や不随意運動を軽減するため、ドーパミン 作動薬や鉄剤が処方されることがあります。これに加え、生活習慣の見直しや運動療法を取り入れることで、症状のコントロールが期待できます。
適切な治療を受けることで、睡眠中の不快感や動きを軽減し、快適な睡眠を取り戻すことが可能です。気になる症状があれば早めに相談してみましょう。
参考
睡眠関連運動障害 | 国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所睡眠・覚醒障害研究部
睡眠時随伴症の場合:脳神経内科・精神科・小児科(子供の場合)
睡眠時随伴症は、睡眠中に異常な行動が起こる疾患で、夢遊病や夜驚症などが該当します。これらは神経系が未発達な子供に多く見られる一方、大人に発症するケースも稀にあります。
症状が見られる場合は、脳神経内科や精神科、子供の場合は小児科の受診を検討しましょう。原因は未解明な部分 が多いものの、まずは寝室の安全対策や睡眠環境の調整を行い、様子を見るのが一般的です。それでも改善が見られない場合には、薬剤の処方や精神療法が必要になることがあります。
こうした治療は専門的な知識を持つ医師が慎重に進めるため、信頼できる診療科やクリニックでの相談が大切です。適切なケアを受けることで、患者本人だけでなく家族の不安も軽減されるでしょう。
参考
睡眠時随伴症 | 国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所睡眠・覚醒障害研究部
睡眠障害で病院に行くメリット

睡眠障害は、病院で専門医の診断を受けることで、より正確な原因が特定され、早期改善が目指せます。この章では、睡眠障害で病院に行くメリットについて解説します。
①正確に原因の診断ができる
睡眠障害で病院に行くことで、原因を正確に診断することができます。
睡眠障害は「眠れない」という共通の症状を持ちながら、原因はストレスや生活習慣の乱れ、身体的・精神的な疾患など多岐にわたります。
専門医の診察を受けることで、その原因を正確に特定し、必要な検査や適切な治療計画を立てることが可能です。自己判断では気づきにくい問題や疾患も、専門的な視点から明らかにできるため、安心して症状に向き合うための重要な一歩となります。
②結果的に早期改善が目指せる
睡眠障害を病院で治療することで、結果的に早期改善につなげることができます。
睡眠障害の治療は、一度の診察で完結するものではなく、継続的な治療と経過観察が求められます。
例えば、睡眠時無呼吸症候群(SAS)の治療に使用されるCPAP療法は、装置を長期的に使い続ける必要があり、定期的に医師が効果を確認しながら治療を進めていきます。
一方、精神的な要因による不眠症では、睡眠薬だけに頼るのではなく、カウンセリングや生活習慣の改善を併用することが重要です。
このように、睡眠障害の治療は原因に合わせた多面的なアプローチが必要なため、時間がかかるように思えて病院の受診をためらう人もいるでしょう。しかし、専門医とともに一歩ずつ進めることで、結果として早期の改善を実現し、健康的な睡眠を取り戻すことが期待できます。
睡眠障害で病院に行く目安は?何科に行くべきか自己診断してみよう

睡眠障害は原因や症状に応じて受診すべき診療科が異なります。この章では、具体的な症状や状況別に、適切な診療科を判断するための目安を解説します。
メンタルの不調やストレスがあるときは何科にいけばいい?
メンタルの不調やストレスが原因で眠れない場合は、心療内科や精神科の受診がおすすめです。
精神的な不調は睡眠の質を大きく左右すると言われています。これらの診療科では、カウンセリングや認知行動療法、必要に応じた薬物療法を通じて、心と体のバランスを整える治療が行われます。
メンタルヘルスに特化した治療を受けることで、根本的な原因にアプローチし、改善を目指すことができるでしょう。
生活習慣が乱れているときは何科にいけばいい?
不規則な生活習慣が原因で睡眠障害が起こっている場合は、まず内科を受診するのがおすすめです。
生活習慣の乱れは、睡眠リズムや体内時計に影響を与え、不眠や過眠の原因となることがあります。内科では、患者の生活スタイルを詳しくヒアリングしたうえで、睡眠改善に向けたアドバイスや必要に応じた薬剤の処方を受けることができます。
また、場合によっては心療内科や精神科を紹介されることもあります。不規則な生活が続いていると、自力で改善するのは難しいことも多いため、専門家の力を借りて生活リズムを整えることが大切です。
いびきがあるときは何科にいけばいい?
いびきが気になる場合は、耳鼻咽喉科や呼吸器内科、いびき外来の受診がおすすめです。特に、睡眠中にいびきがひどく、呼吸が止まるような場合は、睡眠時無呼吸症候群(SAS)の可能性があります。
医療機関では、いびき・睡眠外来の専門医の診察によって、いびきの原因を詳しく調べます。治療法としては、CPAP(持続陽圧呼吸療法)やマウスピース治療、いびきレーザー治療などが一般的です。いびきは放置すると生活の質を低下させるだけでなく、健康リスクを高めることもあるため、早めの受診が大切です。
<いびきの根本治療ができる「いびきメディカルクリニック」の詳細はこちら>
下肢がむずむずして眠れないときは何科にいけばいい?
下肢がむずむずして眠れない場合は、脳神経内科を受診するのがおすすめです。この症状は「むずむず脚症候群(レストレスレッグス症候群)」の可能性があり、足に不快感やむずむずした感覚が生じることで睡眠が妨げられる疾患です。特に、夜間や横になったときに症状が悪化するのが特徴で、軽度の場合でも睡眠不足を引き起こすことがあります。
他にも、睡眠中に下肢が無意識に動く周期性四肢運動障害も脳の神経系の異常が原因と考えられているため、脳神経内科を受診するのが有効でしょう。
脳神経内科では、問診を通じて原因を特定し、鉄剤の処方やドパミン作動薬などの治療が行われます。症状が気になる場合は、早めに専門医に相談して、適切な治療を受けることが大切です。
原因不明で睡眠問題全般の相談に乗ってもらいたいときは何科にいけばいい?
原因が特定できない睡眠の問題に悩んでいる場合は、睡眠外来を受診するのがおすすめです。睡眠外来は、睡眠に特化した診療科で、不眠症や過眠症、睡眠時無呼吸症候群(SAS)など幅広い睡眠障害に対応しています。原因が明確でない症状でも、専門的な診察や検査を通じて、問題の背景を詳しく調べることが可能です。
睡眠外来では、問診、視診、触診、打診等の診察を行い、身体的・精神的な原因を包括的に評価します。また、治療には生活習慣の改善指導や薬物療法、光療法など、個々の症状に合わせたプランが提案されます。
睡眠に関する悩みを一人で抱え込まず、専門の医療機関に相談することで、快適な睡眠を取り戻す道が開けるでしょう。
睡眠障害でお悩みの方は新宿うるおいこころのクリニックへご相談ください

今回は、睡眠障害の代表的な疾患やその原因、診療科の選び方について解説しました。睡眠障害は、「眠れない」「眠りが浅い」「日中に異常な眠気がある」といった共通の症状を持ちながら、その背景にはストレスや生活習慣の乱れ、さらには疾患が隠れていることもあります。
適切な診療科を受診し、専門医による診断を受けることで、根本的な原因を特定し、適切な治療を始めることが重要です。
新宿うるおいこころのクリニックでは、不眠症などの精神科・心療内科が診療科目である睡眠障害に関する治療を行っています。原因を詳しく調べた上で、認知行動療法や薬物療法など、一人ひとりに合わせた治療を提案します。軽い症状でも改善が期待できるため、「何となく眠れない」といった悩みでもお気軽にご相談ください。適切なサポートを受けて、質の高い睡眠を取り戻しましょう。
よくある質問
睡眠障害とはなんですか?
睡眠障害とは、眠ることに関わる問題が生じる疾患の総称です。現代の生活環境や働き方の変化により、十分な睡眠を確保するのが難しくなる中、多くの人が何らかの睡眠障害を経験しています。
睡眠の問題全般の相談に乗ってもらいたいときは何科にいけばいい?
睡眠の問題に悩んでいる場合は、睡眠外来を受診するのがおすすめです。睡眠外来は、睡眠に特化した診療科で、幅広い睡眠障害に対応しています。
![【公式】新宿うるおいこころのクリニック | 新宿の心療内科・精神科[東京新宿駅徒歩3分]](https://uruoi-clinic.jp/wp-content/themes/uruoi/assets/img/logo-b.svg)


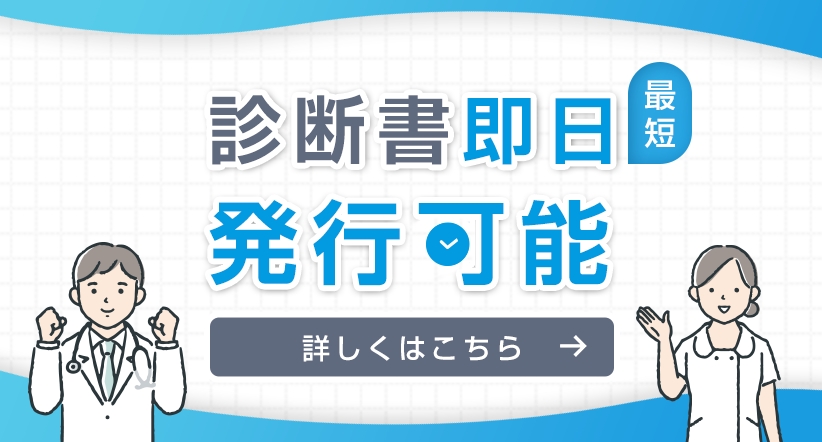




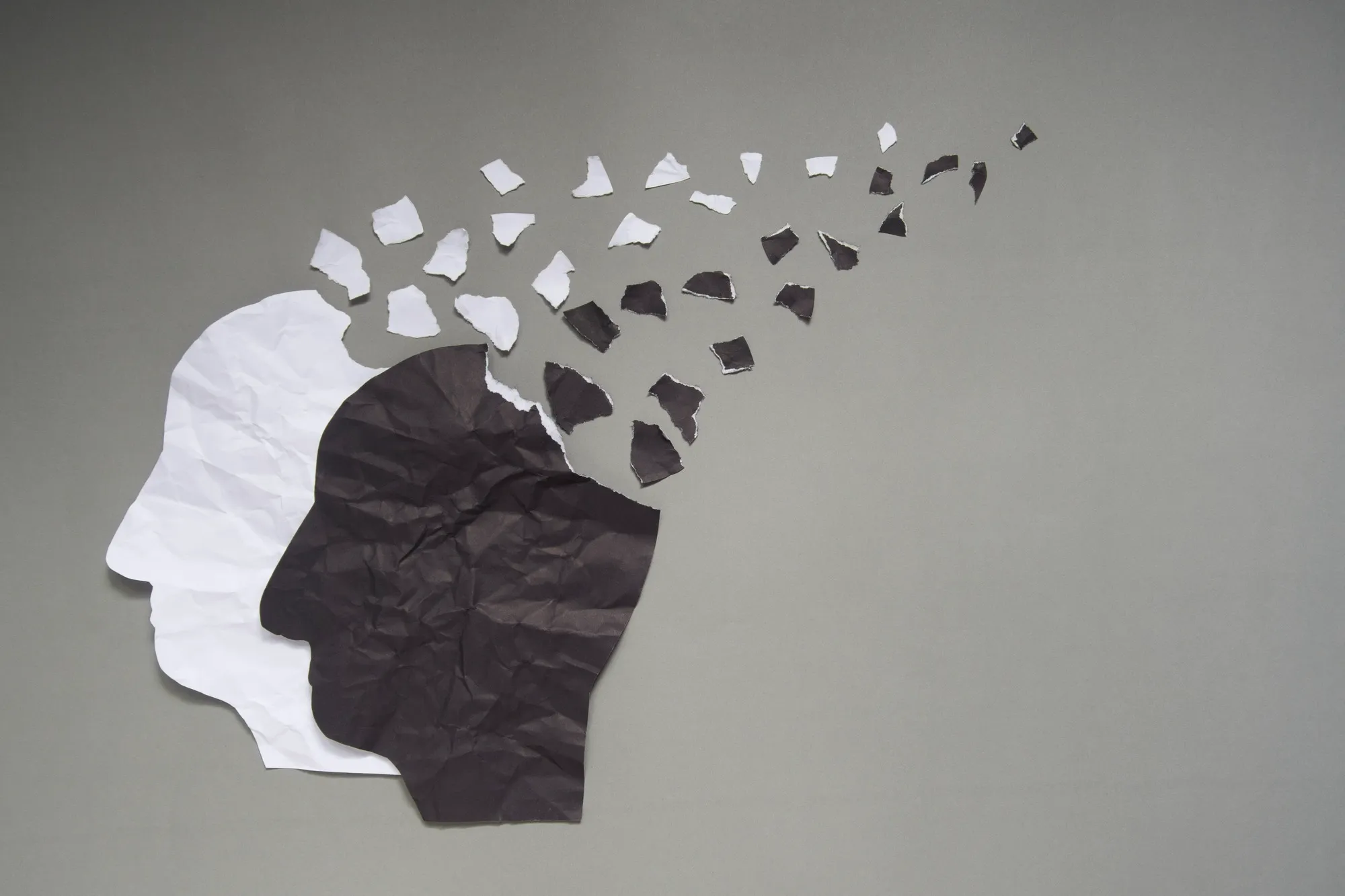









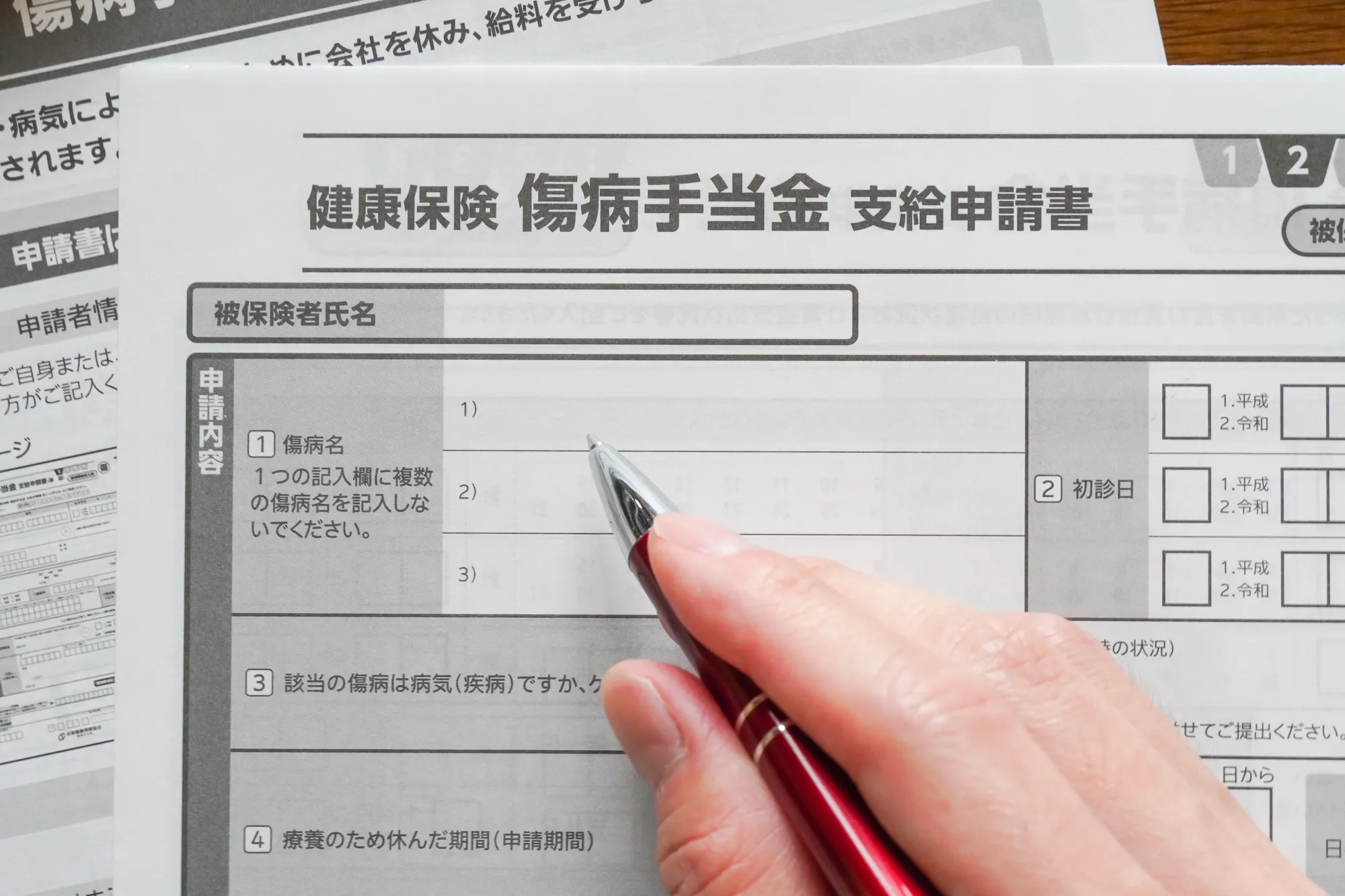




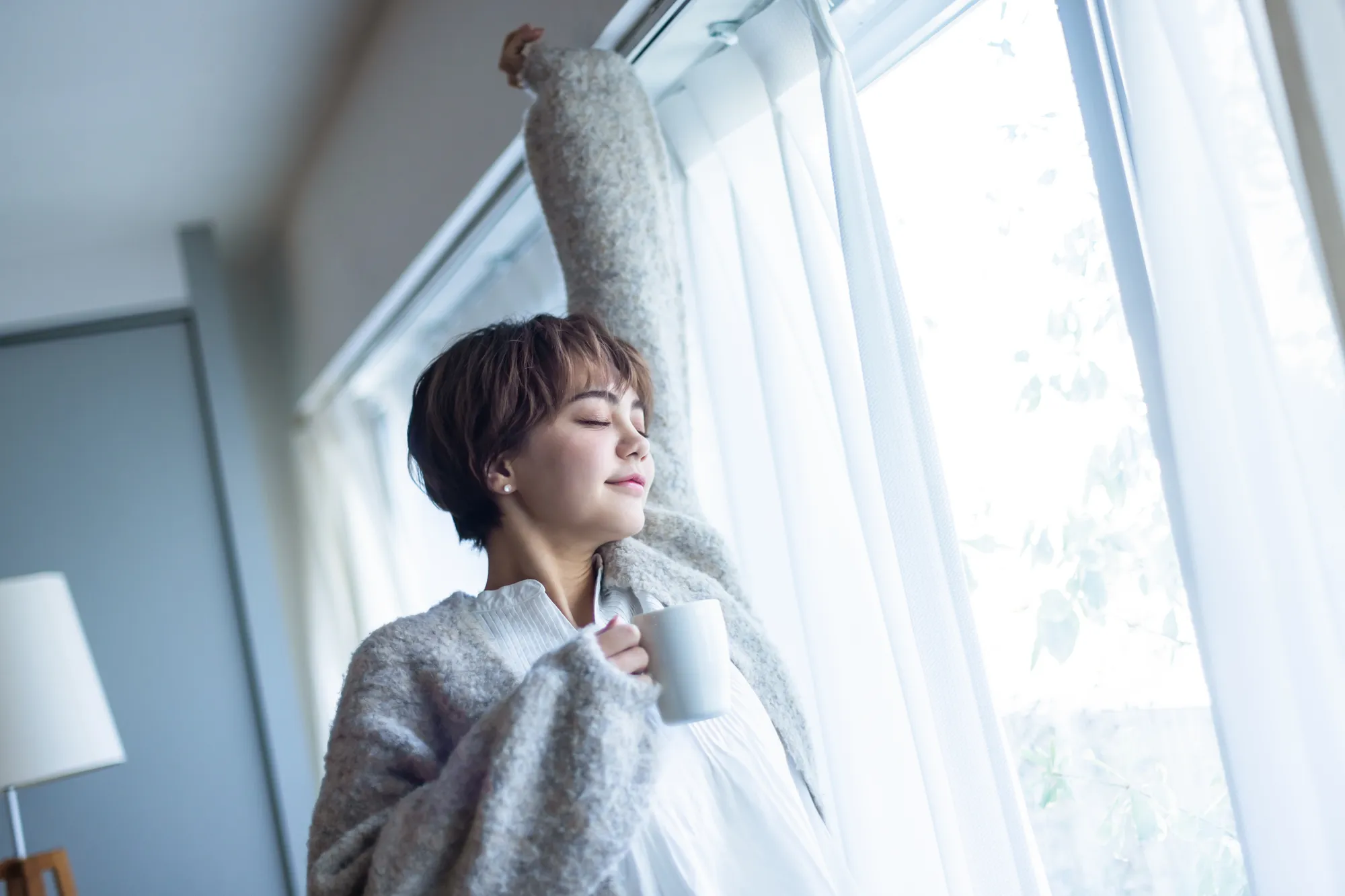
![【公式】新宿うるおいこころのクリニック | 新宿の心療内科・精神科[東京新宿駅徒歩3分]](https://uruoi-clinic.jp/wp-content/themes/uruoi/assets/img/logo.webp)




