双極性障害(躁うつ病)は、症状の出方によって1型・2型に分類されます。
1型は激しい躁状態がみられる、2型は軽躁状態とうつ状態がみられる、と特徴は異なるため、それぞれの症状例や診断方法を見て違いを知っておくといいでしょう。
この記事では、双極性障害(躁うつ病)1型・2型の特徴や症状例、診断方法を解説します。
「1型・2型で何が違うかわからない」
「双極性障害(躁うつ病)について詳しく知りたい」
と思っている方はぜひ参考にしてみてください。
このコラムの監修医師
新宿うるおいこころのクリニック 院長
大垣 宣敬
患者様が抱えているものは1人1人異なっており、症状の種類や程度も千差万別です。 私たちは患者様からお話を聞くことで悩みを共有し、ご希望や思いを丁寧に汲み取りながら、患者様中心の医療を共に実践していけるよう心がけています。
目次
双極性障害(躁うつ病)1型・2型とは

双極性障害(躁うつ病)は、感情の波が極端に変動する精神疾患で、主に「躁状態」と「うつ状態」が交互に現れることが特徴です。双極性障害(躁うつ病)は、1型と2型という2つのタイプに分かれていて、それぞれに特徴があります。
例えば、双極性障害1型は、激しい躁状態が現れることが特徴です。一方、双極性障害2型は、うつ状態の期間が長く、躁状態は軽度であることが特徴です。
以下では、それぞれのタイプについて詳しく解説するので参考にしてみてください。
双極性障害1型の特徴「激しい躁状態がみられる」
双極性障害1型は、激しい躁状態がみられます。うつ状態もみられますが、躁状態のみが現れている場合でも、双極性障害1型と診断されます。
躁状態では、気分が非常に高揚し、エネルギーが満ち溢れたり通常の生活とは異なる行動をとったりする傾向にあります。過剰な自信を持ち、リスクを顧みずに行動してしまうため、衝動的な買い物や危険な行動が増えるようです。躁状態は、数日から数週間続くことがあり、周囲の人にも危害を与えるケースもあるといわれています。
双極性障害2型の特徴「うつ状態の期間がながい」
双極性障害2型の特徴は、うつ状態と軽度の躁状態(軽躁状態)がみられることです。2型の方は、一般的にうつ状態の方が目立ちやすく、気分の落ち込みが長期間にわたって続く傾向にあるといわれています。そのほかにも、エネルギーや興味が低下し、日常生活を送れなくなったり引きこもりがちになったりする可能性もあるようです。
軽躁状態は、少し気分が高まった程度であることが多く、周囲の人々に気づかれにくいことが特徴です。そのため、双極性障害(躁うつ病)ではなくうつ病と診断されるケースも多く、本人も気分の変動に気付いていないパターンがあるといわれています。
参考
双極性障害とは|順天堂大学医学部/大学院医学研究科 気分障害分子病態学講座 精神医学講座・ゲノミクス研究プロジェクト
双極性障害1型と2型の特徴的な症状からみる違い
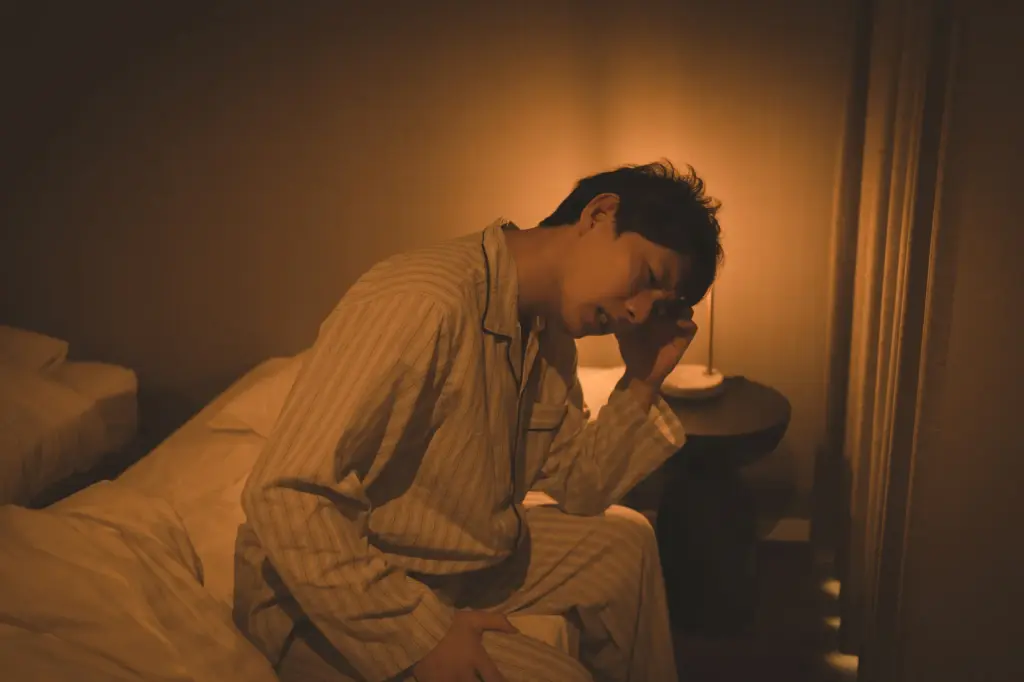
双極性障害1型では、過度の自信や妄想を伴う行動がみられ、突発的に喧嘩をしたり、眠らずしゃべり続けたりする症状があらわれるようです。一方、双極性障害2型は躁状態が軽度なことが特徴なため、躁状態で気分が高くなっている状態をうつ病が回復したと勘違いしたり、ひどいうつ状態に悩まされたりするといわれています。
いずれのタイプでも、症状がみられた際は病院へ行き診断を受けることが大切です。それぞれの違いを知っておくと自身の状態を判断しやすくなるので、双極性障害1型と2型の特徴的な症状例をみてみましょう。
双極性障害1型の主な症状例
双極性障害1型では、躁状態がしっかりあらわれます。ほとんどの場合うつ状態もあらわれますが、躁状態になると、普段は慎重な性格の人でも、突然高額な買い物を始めたり、無謀な投資に手を出したりする行動がみられることがあります。特に金銭感覚が極端に鈍くなり、クレジットカードの限度額いっぱいまで使ってしまうという場面も少なくありません。
また、睡眠時間が極端に短くなる症状も出る傾向にあり、2〜3時間しか眠らなくても疲労を感じず、数日間ほとんど眠らずに活動し続けることもあるようです。職場では、突然大きなプロジェクトを立ち上げたり、実現不可能な計画を熱心に提案したりするなど、周囲を困惑させる行動がみられるといわれています。
そのほかにも、思考が非常に速くなり、次々と考えが浮かぶ状態になることも特徴的です。会話中に話題が飛躍的に変わったり、周囲が理解できないほど早口になったりすることがあり、一つの話題から別の話題へと唐突に移り、周囲の混乱を招くことも少なくないといわれています。自分には特別な能力や使命があると信じる誇大妄想が生じるケースもみられ、「自分は特別な才能を持っている」と主張したり、実際の能力以上の仕事を引き受けたりすることもあるようです。
双極性障害2型の主な症状例
双極性障害2型では、うつ状態と軽躁状態がみられます。軽躁状態は、躁状態に比べて気分の高揚が軽く、人によっては症状に気づかない人もいるようです。
また、双極性障害2型でみられるうつ状態は、長期間にわたって続く傾向にあります。例えば、日常的な活動への興味や喜びを完全に失い、「何をしても楽しくない」と感じたり、朝起きるのが極端に困難になったりするといわれています。
うつ状態になることで、仕事や学校に行く準備をするだけでも大きな労力を要し、シャワーを浴びることさえ困難に感じる日が何週間も続くケースがあるようです。また、食欲の変化も大きく出ることがあり、極端に食欲が落ちて体重が減少したり、過食になって体重が増加したりすると考えられています。
双極性障害(躁うつ病)の診断方法

双極性障害1型2型を診断する際は、躁・軽躁病エピソード、抑うつエピソードの現在みられる症状、過去にみられた症状を確認し、症状の組み合わせによって双極性障害1型と双極性障害2型のどちらに当てはまるのか判断していきます。
また、診断する際は、躁病エピソードは1週間以上、軽躁病エピソードは4日間以上、抑うつエピソードは2週間以上、ほぼ毎日1日の大半でみられることが条件として定められています。
また、躁・軽躁病エピソードを見分けるために診断基準が設けられています。症状の程度によって、躁状態と軽躁状態に分類されるので、それぞれの違いをチェックしてみましょう。
躁・軽躁病エピソードの診断方法
躁・軽躁病エピソードの診断では、気分の高揚のほか、活動量の増加も必要条件として定められています。
例えば、テンションが異常に高まっている上に、普段は絶対にしない賭け事や衝動買いをしている場合は躁・軽躁病エピソードの対象となります。気分が高揚していても、特に行動面における変化が見られない場合は、躁・軽躁病エピソードの対象にはなりません。
躁状態か軽躁状態なのかセルフチェックする際は、以下の基準を参考にしてみてください。
- 躁状態:
仕事がままならないほどの問題がある、入院が必要と判断される、など生活での著しい機能障害が伴う場合 - 軽躁状態:
気分の高揚と活動量の増加が伴うが、躁状態には当てはまらない程度の場合
参考
日本うつ病学会診療ガイドライン双極性障害(双極症)2023
双極性障害は1型でも2型でも病院へ行こう

双極性障害の疑いがある場合は、1型でも2型でも病院へ行くことが大切です。
治療を受けることで、気分の波が緩和され、より安定した日常を取り戻すきっかけになるでしょう。また、自分では双極性障害1型と認識していても、実は不安障害などの別の精神疾患だったり、双極性障害2型だったりする可能性もあります。
病院では、症状に合わせた治療計画が立てられるので、自分の状態をきちんと把握した上で治療を受けられ、より負担の少ない効率的な改善を目指せます。
双極性障害の治療では1型と2型で同じ薬物療法が採用される
双極性障害1型と2型は、症状や発症のメカニズムが異なるものの、薬物療法においては基本的に同様の薬が採用されます。使用する薬としては、気分安定薬や非定型抗精神病薬などが主に使用されますが、種類ごとに主な効果が異なるので、医師の指示に従い服用することが大切です。
薬物療法をすると症状改善を見込めます。ただし、双極性障害2型は、薬物療法のみでは不十分と考えられているので注意が必要です。また、躁状態が軽度なことから治ったのか判断しにくく、治療の目的を見失いやすくなるともいわれています。
双極性障害は精神科・心療内科へ相談
双極性障害の疑いがある場合、精神科・心療内科へ相談するといいでしょう。精神科や心療内科では、双極性障害を含むさまざまな精神疾患を専門に扱っているため、適切な診断と治療を受けられるでしょう。必要に応じて、薬物療法や心理療法の組み合わせを行ったり、診断書を書いて休職を進めたりするため、心身の負担を抑えながら根本改善を目指せます。
また、双極性障害ではない別の精神疾患が見つかった場合でも、精神科・心療内科であればそのまま対応可能です。新たに病院を探すことなく治療を始められるので、精神的な負担を抑えられるでしょう。
双極性障害1型・2型の診断は新宿こころのうるおいクリニックへご相談ください
新宿うるおいこころのクリニックでは、双極性障害1型・2型の診断に対応しています。
診断では、症状や進行具合に応じた治し方を提案することで、一人ひとりに合わせた症状改善を目指せます。また、治療にあたり生じる患者様の不安を減らすため、「副作用が怖い」などの声もしっかりとお聞きします。
双極性障害(躁うつ病)は放置せず治すことが大切なので、どうぞお気軽にご相談ください。
よくある質問
双極性障害の方の話し方に特徴はありますか?
双極性障害の方の話し方に、特定の一般的な特徴があるとは言えません。双極性障害は気分の波が特徴的な疾患ですが、話し方のパターンは個人によって大きく異なります。それぞれの方が持つ個性、生活環境、文化的背景などの要素が話し方に影響するため、双極性障害だけを理由に特定の話し方の特徴を一律に当てはめることはできません。
ただし、双極性障害の症状の状態によって、一時的に話し方に変化が現れることはあります。例えば、躁状態にある時は、普段よりも早口になったり、声が大きくなったり、話が途切れにくくなることがあります。また、次々と新しいアイデアが浮かび、話題が頻繁に変わることもあるでしょう。一方、うつ状態にある時は、話すスピードが遅くなったり声が小さくなったり、言葉数が少なくなったりすることがあります。
真面目な人は双極性障害になりやすい性格というのは本当ですか?
「真面目な人は双極性障害になりやすい」という見解は、医学的に確立された事実ではありません。双極性障害の発症原因は判明しておらず、遺伝的要因や脳内の神経伝達物質の異常、環境要因など、複数の要素が複雑に絡み合っているため、性格だけが原因となることはないと考えられています。
ただし、真面目な性格の人は、几帳面で完璧主義な傾向があるため、ストレスを溜め込みやすい可能性があります。責任感が強く、周囲の期待に応えようと努力するあまり、自分の限界を超えて無理をしてしまうこともあるでしょう。このようなストレスの蓄積が、精神的な健康に影響を及ぼす可能性はあるといわれています。
双極性障害(躁うつ病)1型・2型って何?それぞれの診断方法は?
この記事の
シェアをする
![【公式】新宿うるおいこころのクリニック | 新宿の心療内科・精神科[東京新宿駅徒歩3分]](https://uruoi-clinic.jp/wp-content/themes/uruoi/assets/img/logo-b.svg)

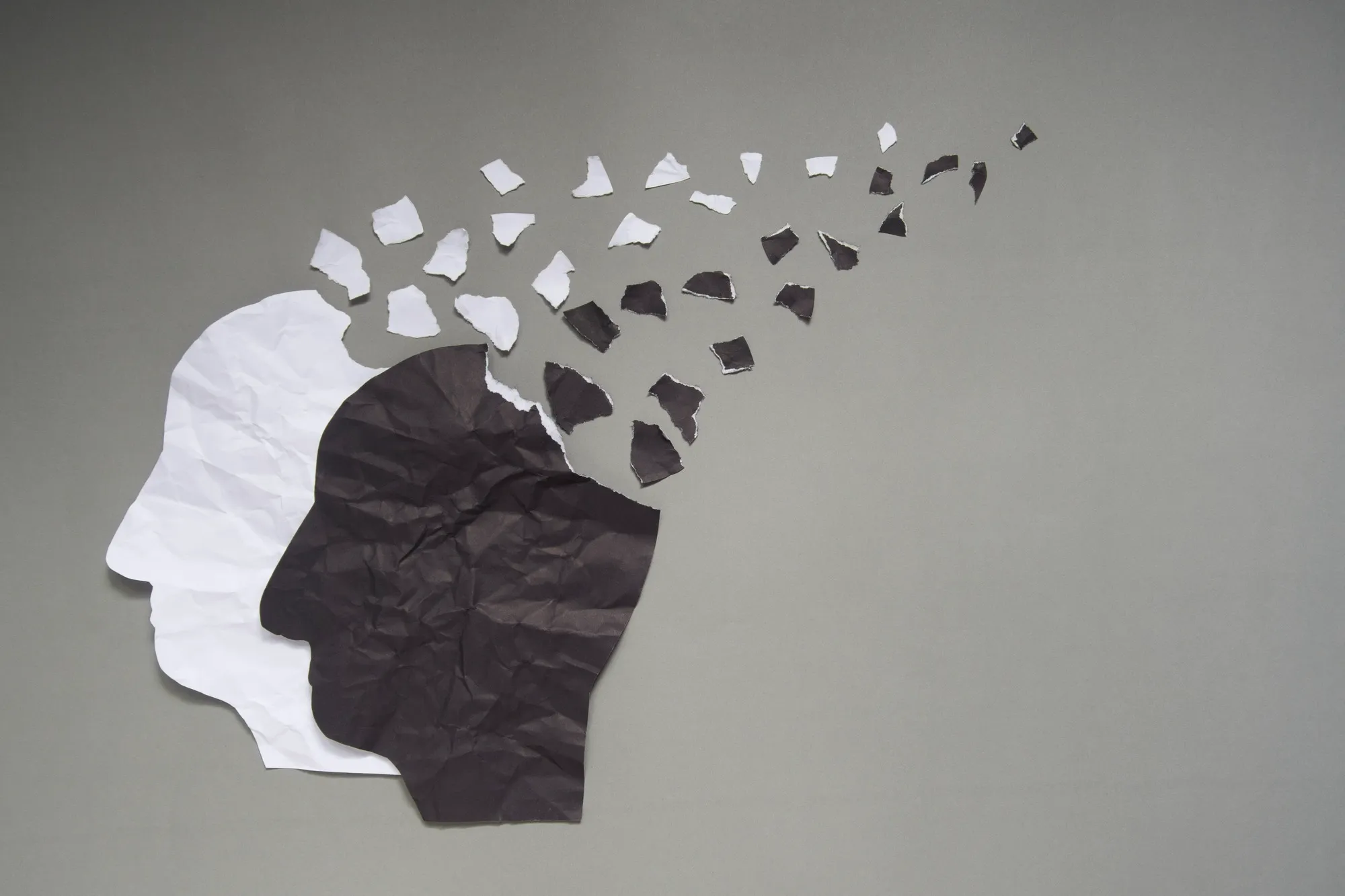
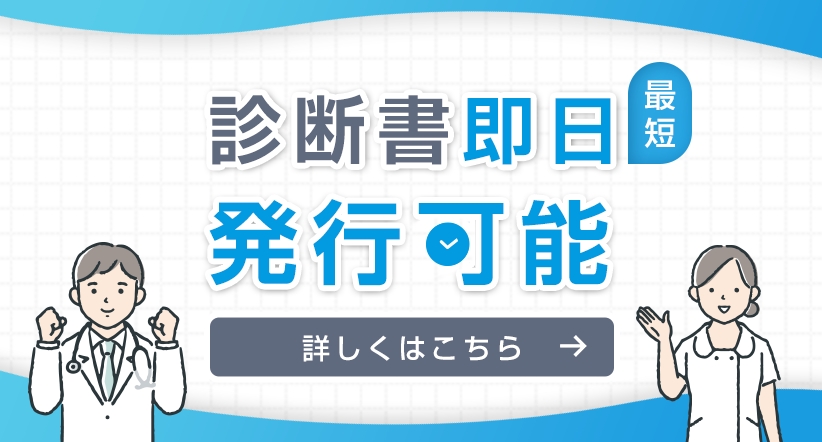





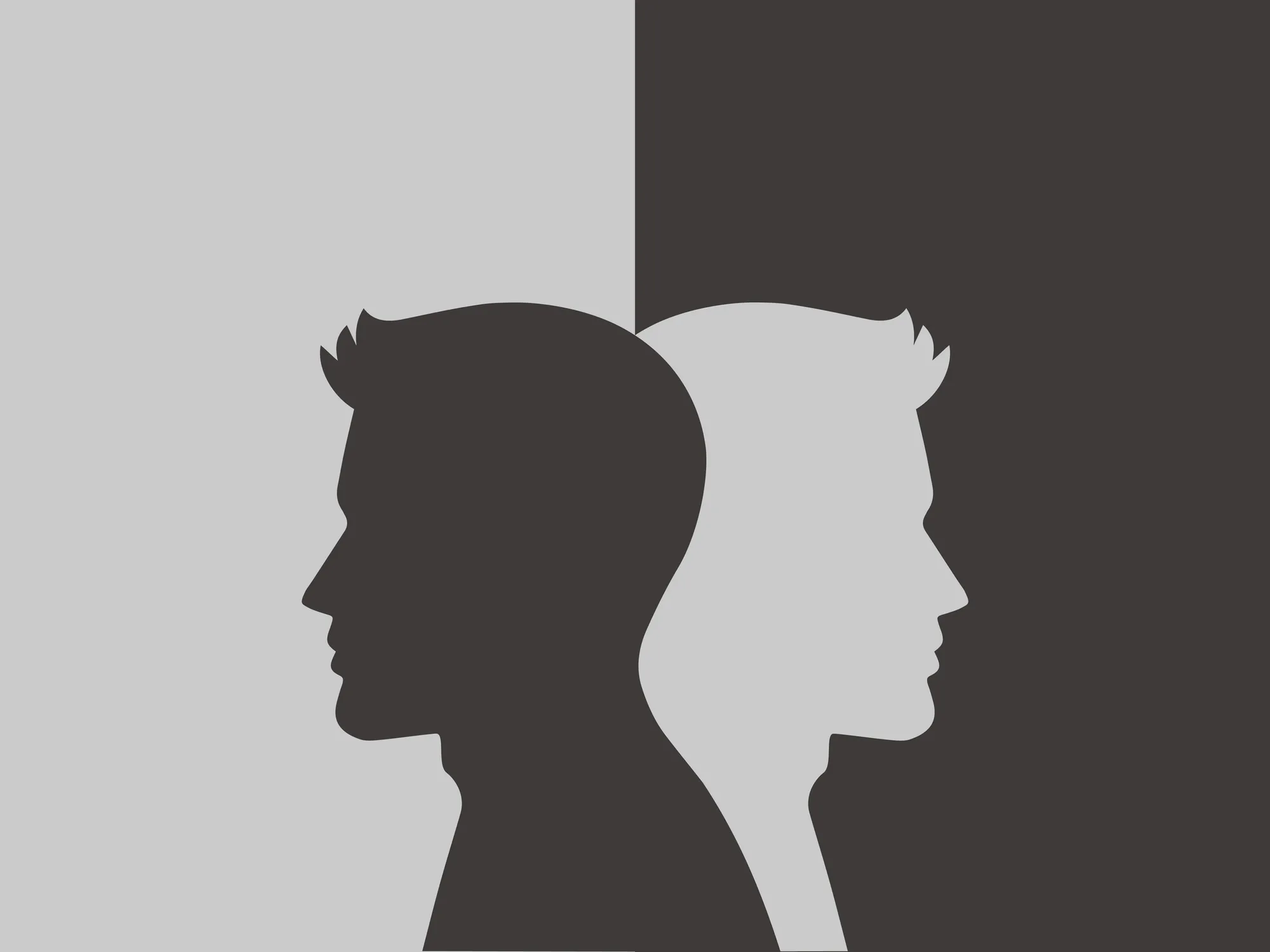









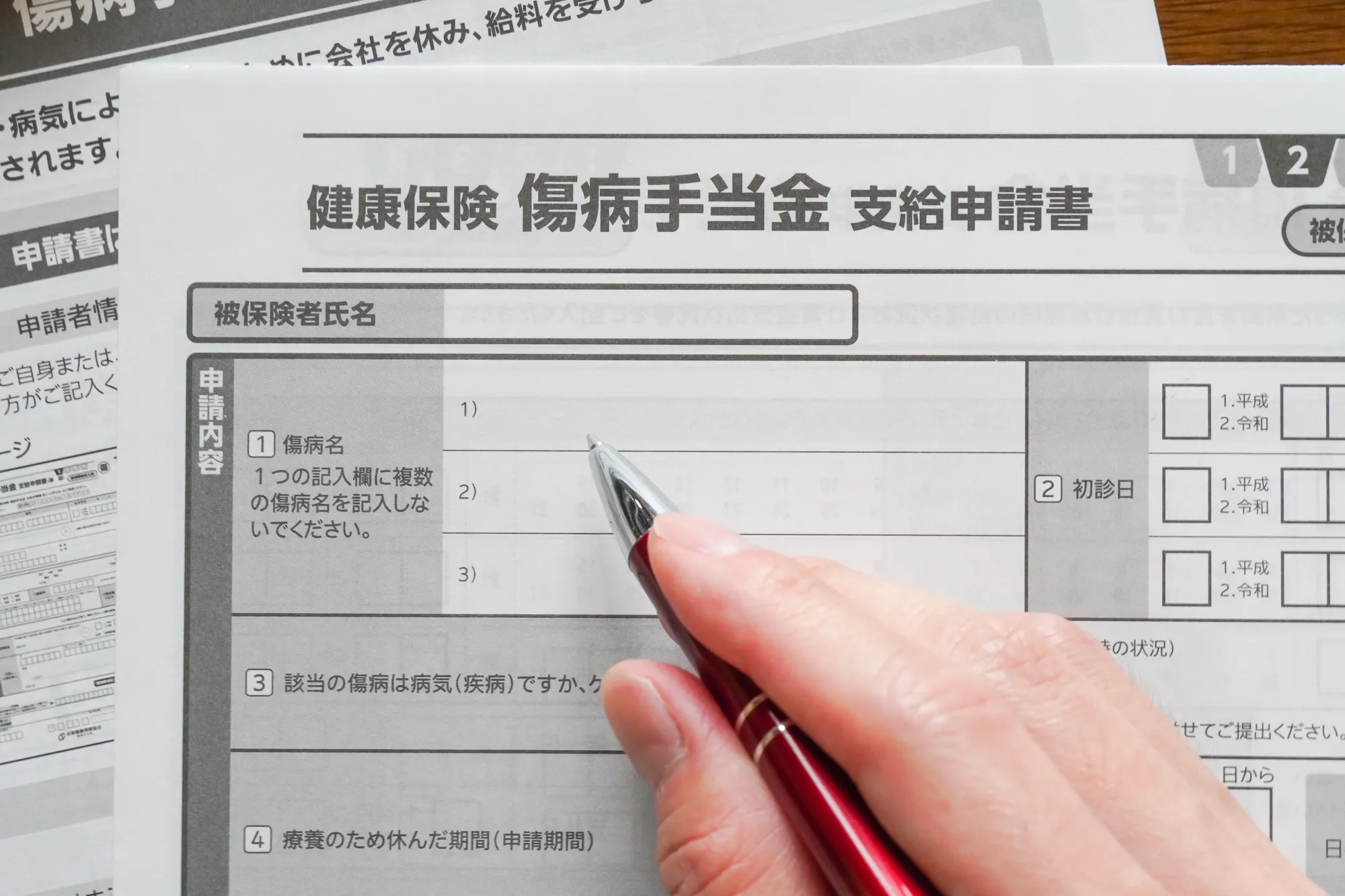




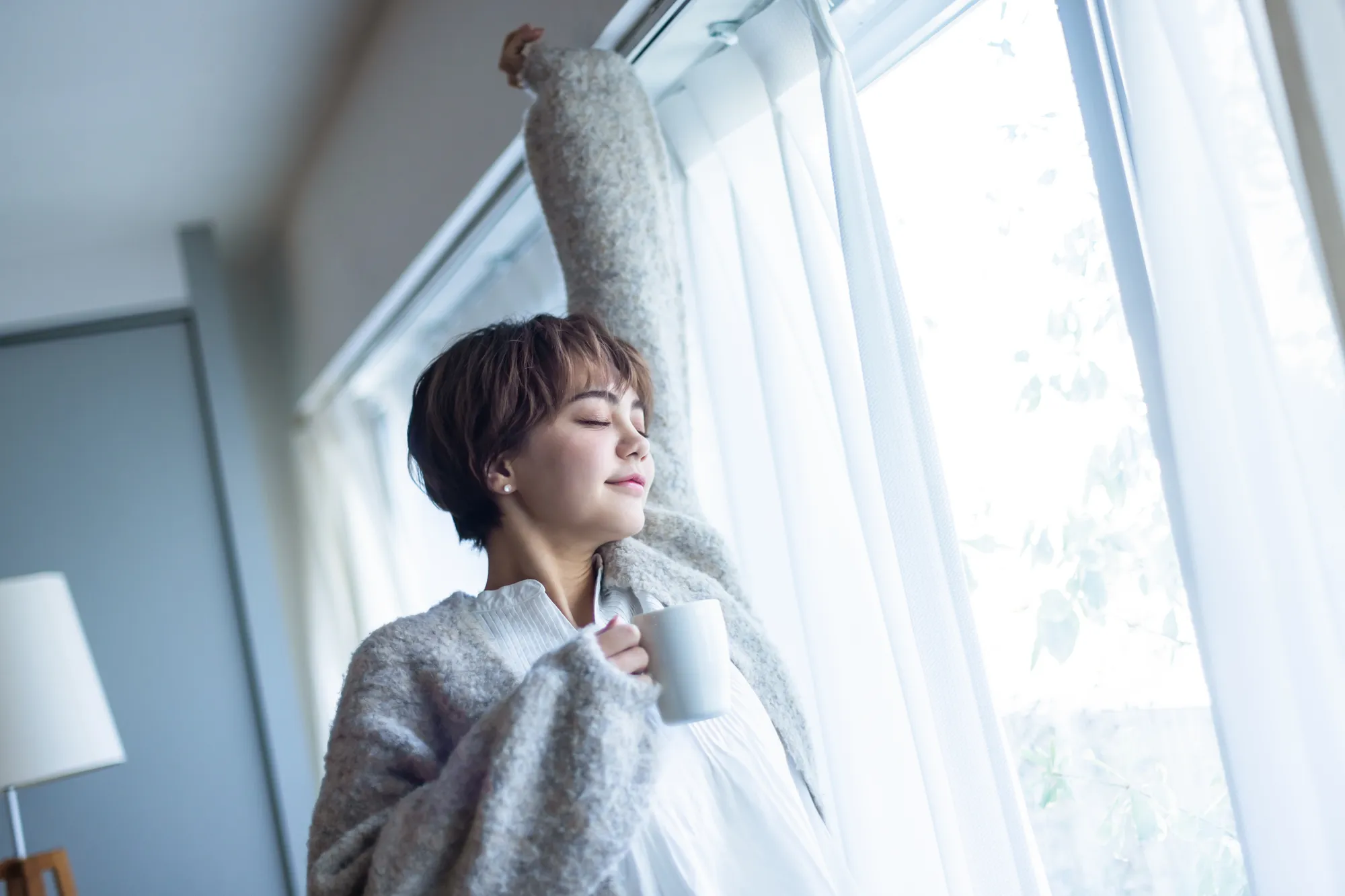
![【公式】新宿うるおいこころのクリニック | 新宿の心療内科・精神科[東京新宿駅徒歩3分]](https://uruoi-clinic.jp/wp-content/themes/uruoi/assets/img/logo.webp)




