自殺や重症化のリスクが伴うため、末路が危ないといわれることも。
治療せず放置すると悪影響を及ぼす可能性がありますが、適切なサポートにより回復を目指せるので、最悪の末路を理解し正しい予防をしておくと良いです。この記事では、双極性障害(躁鬱)の末路が危ないといわれる理由や起こり得る末路、予防法について解説します。
このコラムの監修医師
新宿うるおいこころのクリニック 院長
大垣 宣敬
患者様が抱えているものは1人1人異なっており、症状の種類や程度も千差万別です。 私たちは患者様からお話を聞くことで悩みを共有し、ご希望や思いを丁寧に汲み取りながら、患者様中心の医療を共に実践していけるよう心がけています。
目次
双極性障害(躁鬱)の末路が危ないといわれる理由は?

双極性障害(躁鬱)は、悪化すると深刻な影響を及ぼすといわれている精神疾患です。繰り返される躁状態と抑うつ状態により、薬物依存や自殺リスクが増えたり、幻覚・妄想症状に悩まされたりすることがあります。
また、パーキンソン病の発症や肥満リスクも高まると考えられており、身体的な健康問題の悪化が起こるようです。このような背景から、双極性障害を持つ人の末路は危険といわれることがあり、早期の適切なケアが大切とされています。
寿命が短いといわれているから
双極性障害を含む精神疾患を抱えている人は、健康な人に比べて平均寿命が20年以上短いと考えられています。
主な原因としては、心血管疾患や自殺があげられ、病気に伴う精神的な負担が心身に影響を及ぼすことで健康格差を引き起こしているようです。また、双極性障害が心疾患の合併に関連している可能性も考えられており、高血圧への影響が指摘されています。
参考
・精神疾患を持つ人の平均余命は一般人口に比べて 20 年以上短い ~精神障がい者の健康格差~|東京大学
・双極性障害における精神病歴と心血管疾患との関連
パーキンソン病を発症しやすいから
双極性障害の患者は、パーキンソン病を発症するリスクが高いといわれています。
パーキンソン病は、脳のドーパミン不足によって引き起こされる病気で、震えや筋肉のこわばりといった運動機能に障害が現れます。
発症すると、手足の震えから箸が持ちにくくなったり、体が勝手に動くようになったりするため、1人での外出が困難になる人もいるようです。
肥満リスクが高まるから
双極性障害の患者は、食欲がコントロールできなくなったり、ストレスから過食になったりすることから肥満リスクが高くなるようです。
また、薬物療法で用いる薬の副作用として、体重増加がみられるケースもあります。
実際に、双極性障害を抱えている成人は、健康な人に比べて肥満になる可能性が60%以上高いと報告されているほか、Ⅱ型糖尿病やメタボリックシンドロームの発症率も上昇するといわれています。
双極性障害の原因に関しては下記記事で詳しく解説しています。併せてご覧ください。
双極性障害(躁鬱)を放置すると起こり得る末路

双極性障害(躁鬱)を放置すると、酷いうつ状態から何も手につかなくなったり、躁状態が悪化して問題行動を起こしたりするリスクが高まります。
最悪の場合、自殺願望が強くなり命を落とす危険性もあるので、起こり得る末路をチェックして適切なサポートを受けるようにしましょう。
双極性障害(躁鬱)を放置すると起こり得る末路①「うつ状態が重症化して何もできなくなる」
双極性障害が長期にわたり続くと、うつ状態が重症化することがあります。うつ状態が進行すると、最低限の生活を送るためのエネルギーすら湧かなくなり、食事や睡眠の管理ができなくなるようです。
また、活力の低下から自己嫌悪や絶望感に支配されてしまい、周囲の人と普段通りのコミュニケーションをとることが困難になるケースもあるようです。
精神的な負荷が続くと社会的な孤立を招くリスクも高め、ますます他者との接触を避けるようになるとも考えられています。
双極性障害(躁鬱)を放置すると起こり得る末路②「躁状態で問題を起こし社会的信頼を失う」
躁状態の影響により気分が高揚すると、金銭的な浪費や無謀な投資などの問題を引き起こすことがあります。また、対人関係において不適切な発言をとったり、イライラして喧嘩を起こしたりとトラブルも増えるようです。
問題行動がみられても症状を放置していると、周囲からの社会的信頼を失い、気付いたときにはサポートしてくれる人間がいなくなってしまうかもしれません。
双極性障害(躁鬱)を放置すると起こり得る末路③「自殺を考えるようになる」
放置により抑うつ状態が悪化すると、絶望感で頭がいっぱいになり自殺リスクを高めるといわれています。
「自分は必要のない人間だ」
「何もできないならいない方がマシ」
といったネガティブな思考から逃れるため、命を絶つ選択肢を考え出してしまうようです。
また、躁状態から抑うつ状態へ切り替わる際、感情の激しい起伏が起こると思考が混乱し正常な判断ができなくなるため、衝動的な行動が増えると考えられています。
双極性障害の最悪の末路を防ぐためには、原因を知っておくことも大切です。下記記事では、双極性障害の原因について解説しているのでぜひ参考にしてみてください。
双極性障害(躁鬱)で最悪の末路を回避するためにできること

双極性障害(躁鬱)は、適切な管理とサポートがあれば症状をコントロールでき、最悪の末路の回避を目指せます。
以下では、症状の悪化を防ぐための対策法を紹介するので、日々の生活に取り入れてみましょう。
双極性障害(躁鬱)で最悪の末路を回避するためのポイント①規則正しい生活を心がける
規則正しい生活を心がけることで、体内時計が整えられて気分の安定を促せるといわれています。実際に取り入れる際は、毎日の起床・食事・就寝時間を一定にしたり、適度な運動を行ったりすると良いです。
習慣化により気分が落ち着いてきても、たった一度の徹夜で躁転する可能性があるため、なるべく睡眠時間や生活リズムを乱さないよう意識することが大切です。
双極性障害(躁鬱)で最悪の末路を回避するためのポイント②信頼できる家族や友人にサポートを求める
気分の変動が激しく暴走してしまうこともあるため、症状によっては1人での対処が難しい場合があります。
改善を目指すためには、信頼できる家族や友人にサポートを求めてみましょう。1人で抱えず不安や辛さを共有すると、心の負担軽減につながり、前向きな気持ちで改善を目指せるようになるかもしれません。
双極性障害(躁鬱)で最悪の末路を回避するためのポイント③処方された薬はしっかり飲む
医師から薬を処方された場合は、指示に従い正しく服用することが大切です。効果がみられないからといって、自己判断で服薬を中断したり量を調整したりしてしまうと、症状が悪化する可能性があります。
治療に関して疑問を感じている場合は、自分で何とかしようとせず医師に相談し、経過を確認した上で適切な対応をとることが大切です。医師と連携しながら治療を続けることで、症状のコントロールがしやすくなり最悪の末路を回避できるでしょう。
双極性障害(躁鬱)で最悪の末路を回避するためのポイント④無理をせず周りと比較しない
回復を目指す際は、無理せず自分のペースで頑張ることが大切です。周囲と比較したり無理をしたりしてしまうと、焦りやプレッシャーが生まれて治りづらくなる恐れがあります。
その日の体調や精神状態を最優先に考え、必要なときには休養をとりつつ少しずつ前進することが大切なので、肩の力を抜きながら自分のペースで治療を続けていきましょう。
双極性障害(躁鬱)で最悪の末路を回避するためのポイント⑤自分を受け入れて褒める
双極性障害の悪化を防ぐためには、症状に波があることを理解し、自己嫌悪に陥っても自分を責めず受け入れることが大切です。
また、自身の行動に対して「なんでこんなこともできないんだ」と思うのではなく、「ここまでできて凄い」と優しくしてあげると、精神的なプレッシャーが減って前向きに考えられるようになるでしょう。
双極性障害(躁鬱)の末路を防ぐ予防療法とは
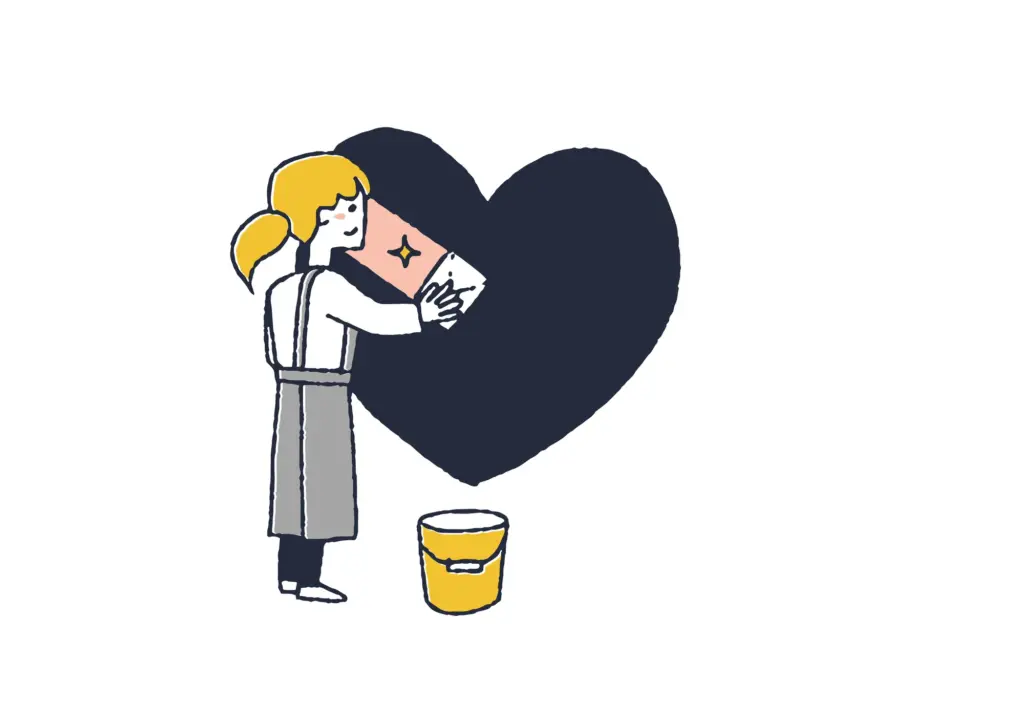
予防療法とは、発症の予防と発症時に軽い症状で抑えることを目的とした治療です。
双極性障害は、予防療法をしないと高確率で再発すると考えられているため、繰り返す再発による最悪の末路を防ぐ上でも大切となります。
治療では、気分安定薬などを用いた薬物療法や、感情面にアプローチする心理社会的治療を行います。また、規則正しい生活や持続的な薬の服用も再発予防になるので、意識しておくことが大切です。
予防療法を行うメリット
症状の再発を防ぎ、安定した生活を実現することは予防療法を行う大きなメリットです。
繰り返される躁鬱が減ることで、以前のように仕事やプライベートを楽しめるかもしれません。また、予防療法を通して症状や感情のコントロール法を知ると、ストレスを多い状況でも冷静に対応しやすくなることもメリットとしてあげられます。
双極性障害(躁鬱)で最悪の末路を防ぐためには自己解決しようとしない

双極性障害の症状がみられた際は、自己解決しようとせず専門的なサポートを受けると良いです。間違った対処法をとると、症状が悪化する恐れがあります。
特に、辛くてどうしようもないときは無理に1人で抱え込まず、医師や周囲の人に相談しましょう。不調を見逃さず適切にケアしていくことが、最悪の末路を防ぐ上で大切となります。
双極性障害(躁鬱)で精神科・心療内科を受診するタイミング
いつもよりイライラする、眠れない、緊張を感じるなど、普段と違う違和感を覚えた際は病院へ受診すると良いです。また、躁状態や抑うつ状態が続いている場合も早めに相談しましょう。
双極性障害の悪化を防ぐためには、早い段階で異変に気付くことが大切です。周囲の人から指摘を受けた際も、自分の状態を受け入れて受診を検討してみてください。
下記記事では、双極性障害のセルフチェック診断テストをご紹介しています。併せてご確認ください。
双極性障害(躁鬱)の診断・治療は新宿うるおいこころのクリニックにご相談ください
今回は、双極性障害(躁鬱)の末路が危ないといわれる理由や起こり得る末路、予防法について解説しました。
双極性障害は、悪化すると薬物依存や自殺リスクが高まることから、末路が危ないといわれています。寿命も健康な人に比べて短いと考えられていますが、適切な治療により改善が期待できるので、双極性障害かも?と思った際は早めに病院へ相談しましょう。
新宿うるおいこころのクリニックでは、双極性障害(躁鬱)の診断・治療に対応しています。
経験豊富な医師が、症状や進行具合に応じた治療提案をすることで、1人ひとりに合わせた症状改善を目指せます。
再発を防ぐためには、正しい治療と継続したサポートが大切です。「家族や友人が統合失調症かもしれない」などのお悩みにも対応していますので、まずはお気軽にご相談ください。
<新宿うるおいこころのクリニックでの双極性障害への治療はこちら>
よくある質問
双極性障害(躁鬱)になりやすい性格はありますか?
感情の波が激しい人、極端に考えがちな人、何事も深く考える過ぎる人は、気付かぬうちにストレスを溜めてしまう傾向にあるため、双極性障害になりやすいといわれています。
双極性障害(躁鬱)の特徴は何ですか?
躁状態では過活動や自信過剰がみられる一方で、うつ状態になると無気力感や興味喪失が続くため、普段通りの日常生活が送れなくなります。
![【公式】新宿うるおいこころのクリニック | 新宿の心療内科・精神科[東京新宿駅徒歩3分]](https://uruoi-clinic.jp/wp-content/themes/uruoi/assets/img/logo-b.svg)




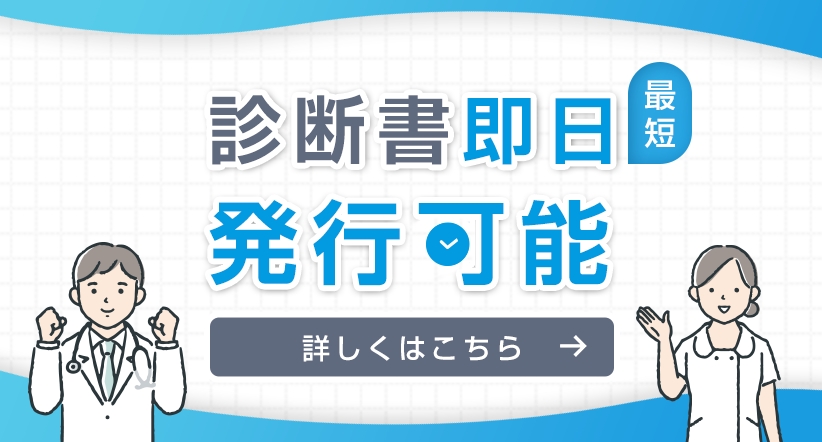




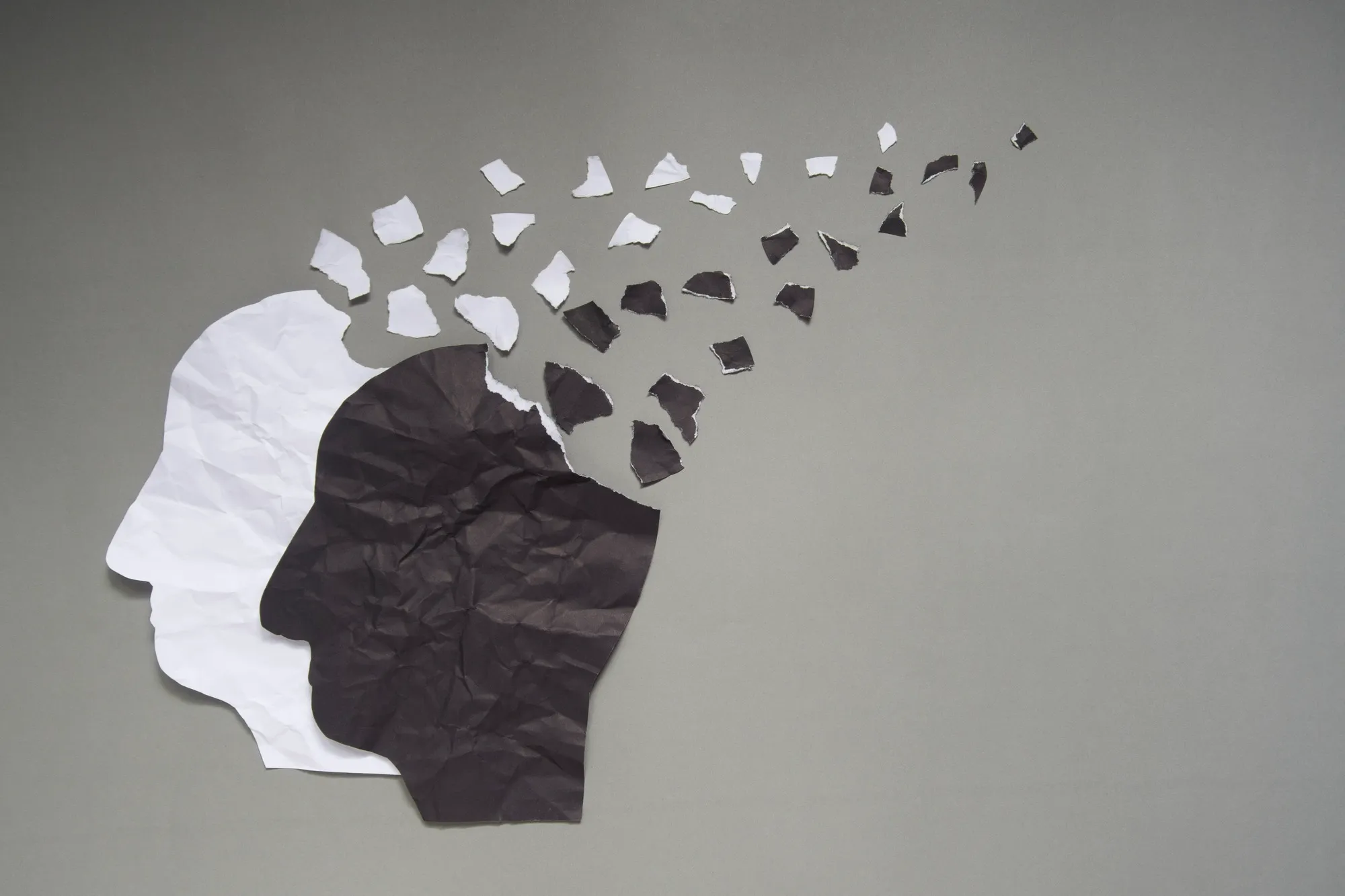
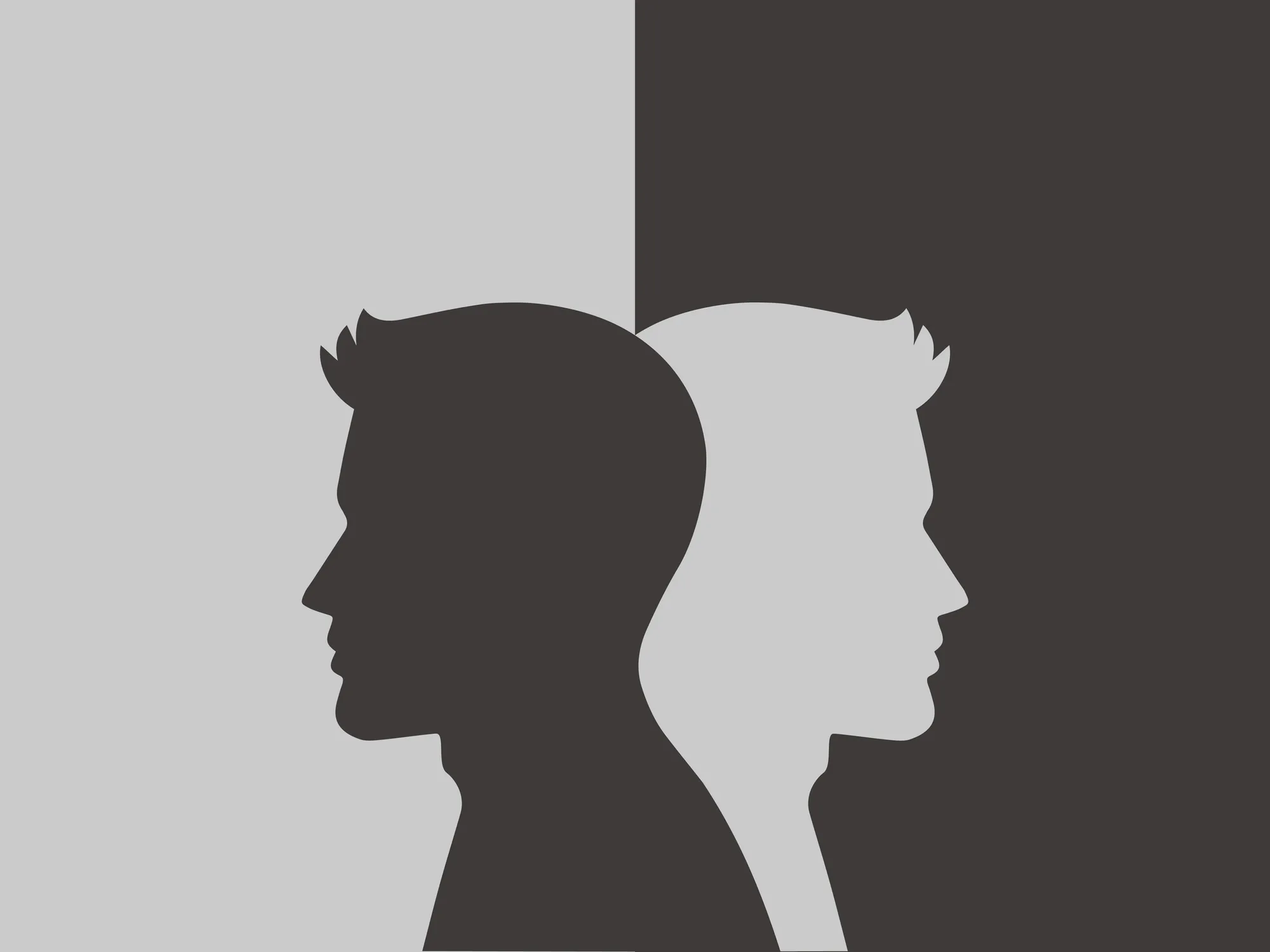








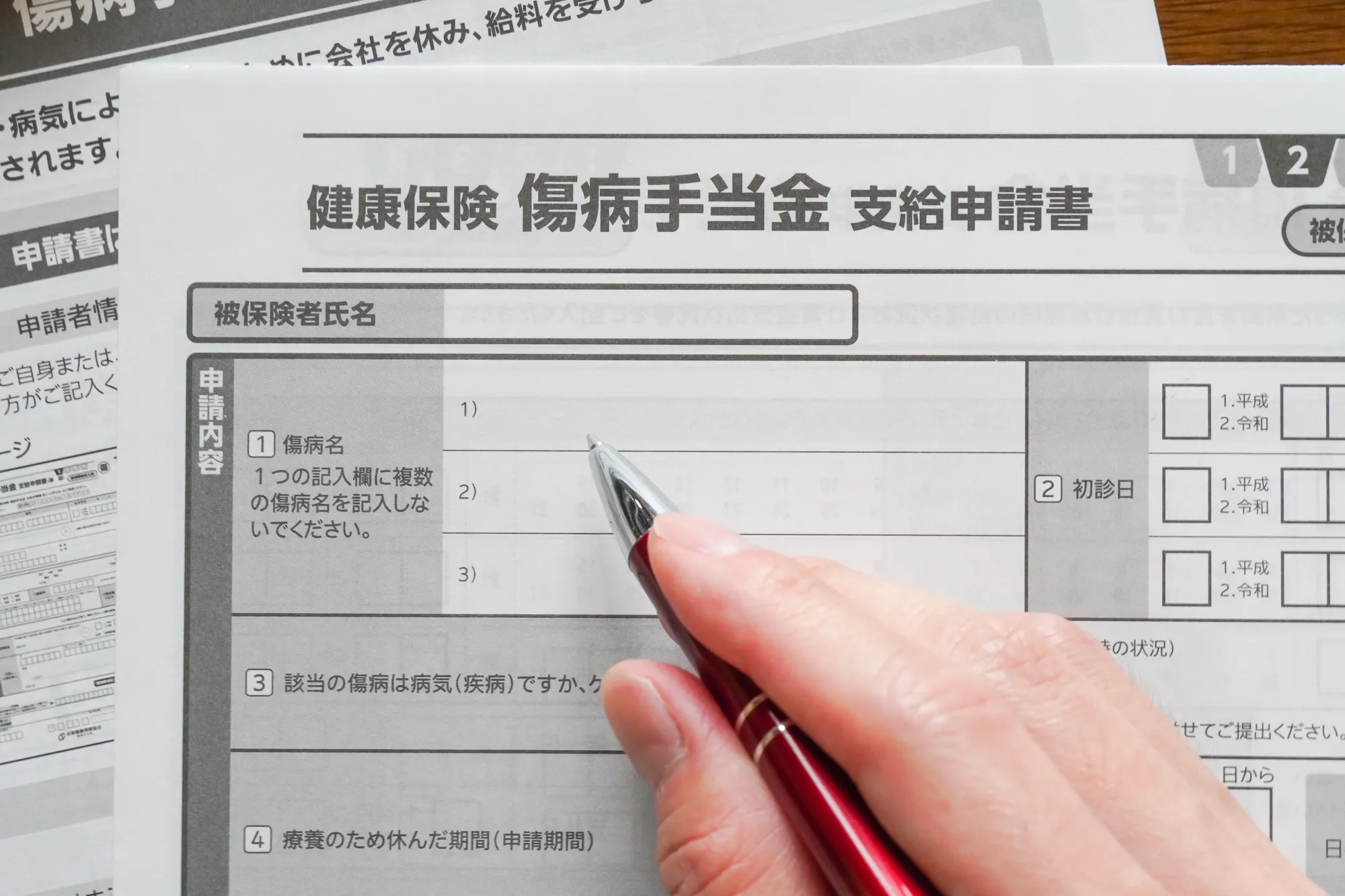




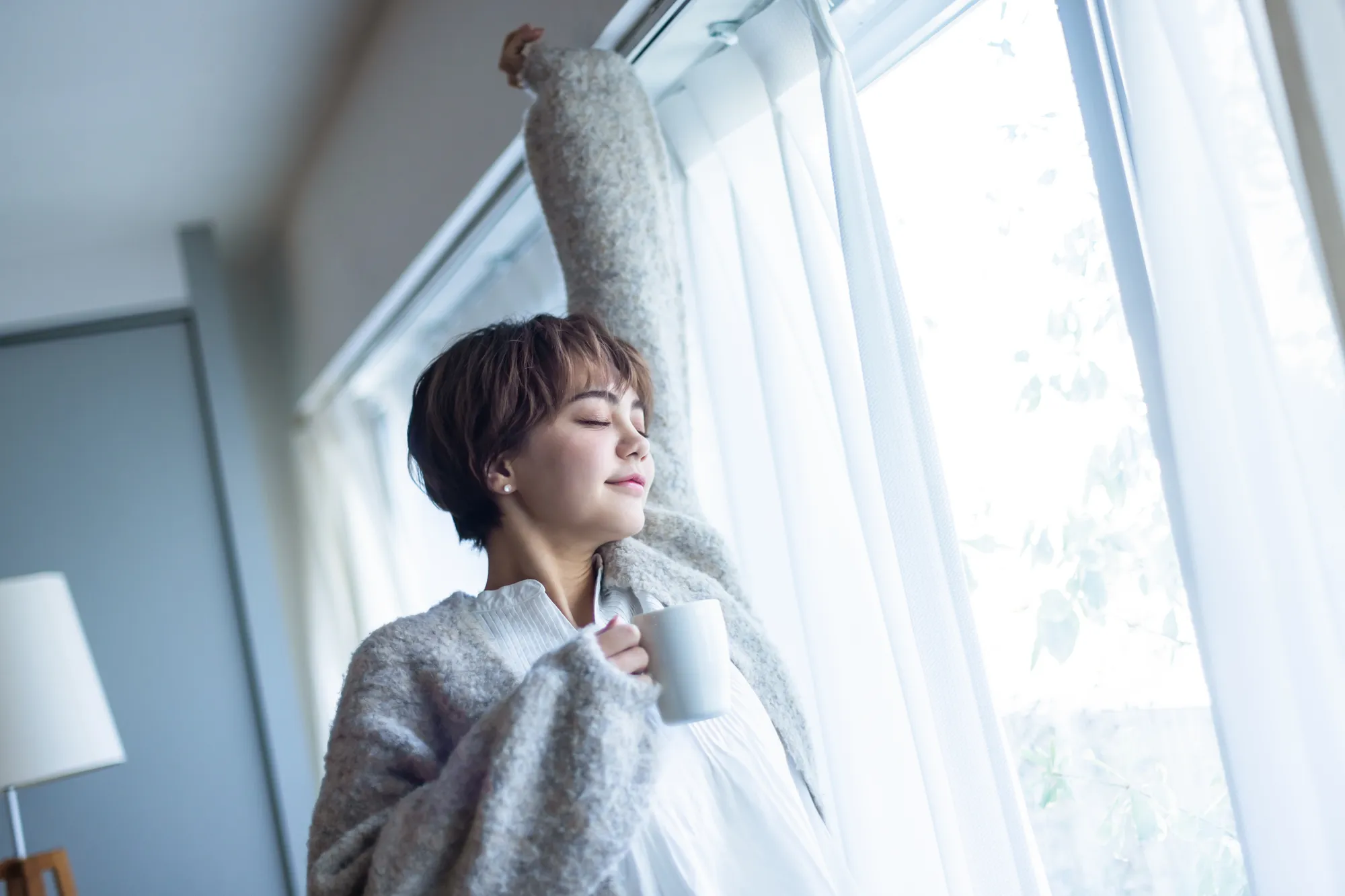
![【公式】新宿うるおいこころのクリニック | 新宿の心療内科・精神科[東京新宿駅徒歩3分]](https://uruoi-clinic.jp/wp-content/themes/uruoi/assets/img/logo.webp)




